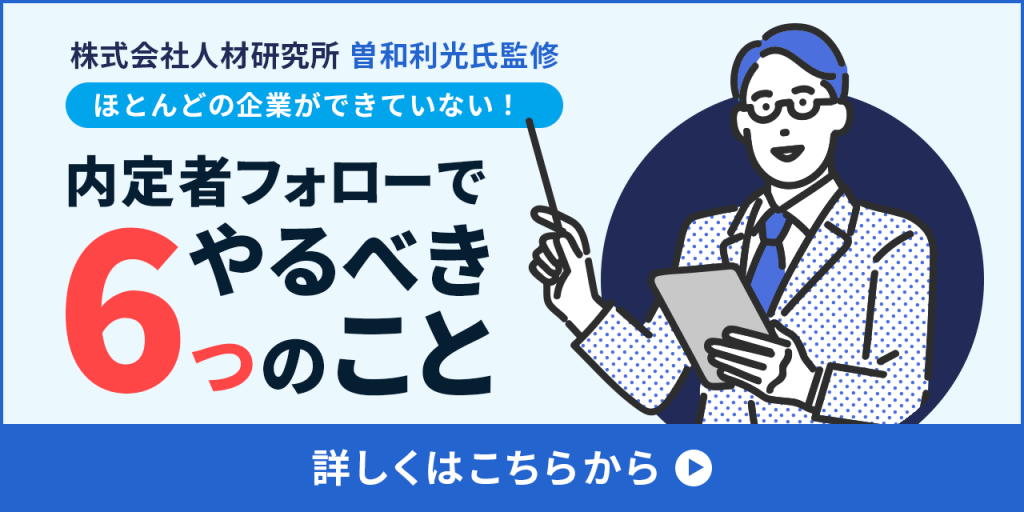お役立ち記事
ハローワークに求人を出すメリット・デメリットとは?費用・方法とともにご紹介
-
- 採用ノウハウ

人材採用の方法としてハローワークの利用を検討しつつも、詳細がわからず一歩踏み出せないでいる採用担当者の方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、ハローワークの概要とともに、ハローワークに求人を出すメリット・デメリットについてご紹介します。あわせて、ハローワークに求人を出す方法とそのポイントも解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
ハローワークとは?まずは概要を知ろう
ハローワークとは、国(厚生労働省)が管轄する公共の就職支援機関のことです。
厚生労働省は「民間の職業紹介事業等では就職へ結びつけることが難しい就職困難者を中心に支援する最後のセーフティネットとしての役割を担う、国(厚生労働省)の機関」と定義しています。つまり、ハローワークとは就職に困っている人を、国が支援して就職の手助けをしてくれる機関なのです。
ハローワークは地域の総合的雇用サービス機関として、職業紹介・雇用保険・雇用対策などの業務を一体的に実施しているため、求人を出す企業も仕事を探している求職者も利用します。全国に設置されており、利用可能時間(開庁時間)は原則「平日の8:30〜17:15」です。一部の施設では、職業相談に限り平日の夜間や土曜日も利用できる場合があります。
参照:ハローワーク|厚生労働省
押さえておこう!ハローワークに求人を出すメリット

企業がハローワークに求人を出すことには、以下のようなメリットがあります。
1.採用にかかる費用を抑えられる
新たに人材を採用するため、求人媒体や人材紹介サービスなどを利用する場合、掲載費や手数料がかかるのが一般的です。その一方で、ハローワークは厚生労働省が管轄する公共の就職支援機関なので、求人を出す際に費用は一切発生しません。そのため、「採用活動にかかる費用を抑えたい」という企業にとくにおすすめです。
2.多くの求職者に求人を見てもらえる
ハローワークを利用する求職者は多く、厚生労働省の発表によると令和2年度の新規求職者数は453.7万人です。1日あたり約13万人が利用している計算になるため、ハローワークに求人を出せば多くの求職者の目に留まり、採用活動を軌道に乗せやすくなると考えられます。
また、ハローワークに申し込んだ求人は、全国のハローワークやハローワークインターネットサービスを通じて、全国の求職者に広く提供される仕組みになっています。そのため、母集団(自社に応募してくれる応募者の集まり)を形成しやすくなるでしょう。
参照:公共職業安定所(ハローワーク)の主な取組と実績|厚生労働省 職業安定局
3.求職者に安心感を与えられる
厚生労働省が管轄しているという点から、ハローワークに求人を出した場合、求職者に安心感を与えることができます。すなわち、求職者の求人に応募するハードルを下げられるということです。
ハローワークは、若年層から高年層まで幅広い年代の求職者が利用しているため、積極的に求人を出すことで求める人材からの応募が期待できます。
4.求人掲載の期間を延ばしやすい
ハローワークの求人掲載期間は「申し込みをした月を含めて3か月間」です。そのため、基本的には公開した月の翌々月の末日で掲載が終了します。
ただし、再掲載を依頼すれば期間を延長することが可能です。面倒な書類作成や手続きは不要なので、手間なく採用活動を続けられます。
5.助成金を得られる場合がある
ハローワークを経由して人材を雇用した場合、一定の条件を満たせば助成金を受給できます。
たとえば、高年齢者や障がい者などの就職困難者を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により継続して雇用した場合は「特定求職者雇用開発助成金」を得られます。具体的な支給額は、対象労働者の類型と企業規模に応じて変わりますが、たとえば「短時間労働者以外の者:高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母など」の場合は60万円となります。
参照:特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)|厚生労働省
意外と知らない!ハローワークに求人を出すデメリット
ハローワークに求人を出すメリットがある一方で、デメリットもあります。
1.事業所情報登録に手間がかかる
ハローワークに求人を出す際は、あらかじめ事業所情報登録を行わなければなりません。具体的には、企業基本情報や事業所詳細情報などを記入する「事業所登録シート」を作成して提出しなければならず、求人媒体や人材紹介サービスを利用する場合と比べて手間がかかります。
ただし、一度事業所情報登録を済ませたらその後はすぐに求人申込書の記入・提出ができるため、この手間は最初だけといえます。
参照:求人申込み手続きの流れ|ハローワーク インターネットサービス
2.採用のミスマッチが起こる可能性がある
ハローワークを利用する求職者は多いですが、必ずしも求める人材から応募が来るとは限りません。そのため、場合によっては採用のミスマッチが起こる可能性があります。
ただし、このデメリットは「求人申込書をなるべく詳細に記入する」「事前にハローワーク職員から応募者の情報を細かく聞き出す」といった工夫で回避できることもあるので、あわせて押さえておきましょう。
正しく知っておこう!ハローワークに求人を出す方法
企業がハローワークに求人を出す方法は、以下のとおりです。
1.事業所情報登録を行う
まずは、ハローワークまたはハローワークインターネットサービスで事業所情報登録を行います。自社の基本情報や特徴、福利厚生などを事前に把握しておき、これらをわかりやすく記載しましょう。
2.求人申込書を作成・提出する
次に、求人申込書を作成します。企業の特徴や仕事内容は詳細に、そして賃金は正確にわかりやすく記入することが大切です。記入した後は、情報の間違いや誤字脱字がないかを必ず確認しましょう。
3.求人票と事務所確認表を受け取る
求人申込書を提出した後、無事に受理されると「求人票」と「事務所確認表」が発行されるため、それを受け取ります。ここまで終えたら申し込みは完了です。
4.求人情報が掲載される
申し込みが完了した求人が、全国のハローワークやハローワークインターネットサービスを通じて、全国の求職者に提供されます。
参照:
求人申込み手続きの流れ|ハローワーク インターネットサービス
応募したくなる求人へ! ~わかりやすい求人で、より良い人材の確保を目指しましょう!~|ハローワーク インターネットサービス
わかりやすさが鍵!ハローワークに求人を出す際のポイント

ハローワークに求人を出す際は、以下のポイントも押さえておくことも大切です。
仕事内容と賃金はわかりやすく記入する
求職者が就職先を選ぶ上でもっとも気にするのは「仕事内容」と「賃金」の2つです。これらを曖昧に記入すると企業と求職者との間にギャップが生じ、ミスマッチにつながりかねません。多くの求職者に応募してもらうためにも、仕事内容と賃金はわかりやすく記入しましょう。
たとえば、営業職を募集する場合は単に「営業職」と記入するのではなく、「どのような商品・サービスをどのような顧客に営業するのか」まで書くのがおすすめです。
賃金については、「基本給」「定額的に支払われる手当」「固定残業代」と個別に記入欄があるので正確に書き、経験者・未経験者で異なる場合はそれぞれ記入しましょう。
参照:応募したくなる求人へ! ~わかりやすい求人で、より良い人材の確保を目指しましょう!~|ハローワーク インターネットサービス
専門用語の使用は避ける
自社では当たり前のように専門用語を使っていたとしても、それを求人申込書に使うのは望ましくありません。とくに未経験者も対象としている求人の場合は、使用を避けることが大切です。
求人申込書に専門用語を使うと、求職者に企業の情報や仕事内容がきちんと伝わりづらくなります。応募が来ない、来たとしてもミスマッチにつながりかねないので、求人申込書は「誰でも理解できる」という点を意識して記入することが大切です。
自社ならではの魅力をアピールする
ハローワークは無料で使える分、求人を出している企業が多いのが特徴です。そのため、他社と差別化できるような求人申込書を作成しなければ、自社の求人が埋もれてしまい、応募がなかなか来ない状況になる可能性があります。
こうした事態を避けるためにも、「資格取得や技能習得などの支援が充実している」「ノルマに追われることなく安定的な収入を得られる」といった自社ならではの魅力をアピールすることが大切です。
参照:応募したくなる求人へ! ~わかりやすい求人で、より良い人材の確保を目指しましょう!~|ハローワーク インターネットサービス
まとめ
ハローワークに求人を出すことには、「採用にかかる費用を抑えられる」「多くの求職者に求人を見てもらえる」「求職者に安心感を与えられる」といったメリットがあります。そのため、採用方法が決まらず悩んでいる場合は、ハローワークを視野に入れるのも一案です。今回ご紹介した方法・ポイントを押さえて、ぜひ利用してみてください。
なお、ハローワークを利用すること以外にも採用方法は複数あります。そのほかの採用方法については以下の記事でご紹介しているので、ぜひあわせてご覧ください。
・最新の採用方法を一挙ご紹介!自社に最適な手法で採用活動を成功させるポイント
・地方の中小企業が取るべき採用手法とは?【採用賢者に聞く 第31回】
・採用ナビはもう古い?採用担当者が知っておきたい採用手法と取り入れ方【採用賢者に聞く 第15回】
また、Thinkings株式会社では採用業務を大幅に効率化する「採用管理システムsonar ATS」を提供しています。「事務作業に追われ、候補者と向き合う時間がない...」とお困りの方は、ぜひ一度資料をご覧ください。
▼導入企業様からはこんなお声をいただいています▼
「採用担当の残業時間が前年より83%減少した」
「まるで採用担当がもう1人増えたみたい」
「最終面接への移行率が60%→90%に増加した」
⇒採用管理システムsonar ATSの資料はこちらから

1,900社以上にご導入された採用管理システム sonar ATSを展開。このお役立ち記事では、採用セミナーレポートやお役立ちコンテンツをはじめ、企業の採用担当者の皆さまに採用に役立つ有益な情報をお届けしています。