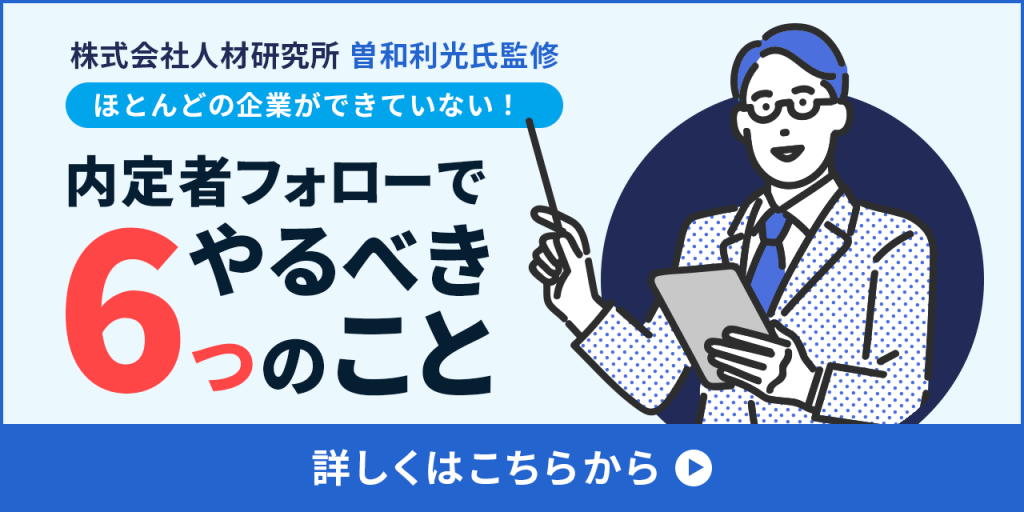お役立ち記事
理解すべき!高年齢雇用継続給付の概要と計算・申請方法
-
- 採用ノウハウ

高齢者雇用とは、労働に対する意欲や業務に関する経験・知識を有する高齢者を雇用することで、人材不足の解消やダイバーシティの実現を図る取り組みのことです。このほか、知識やスキルの伝承、働きやすい環境の整備といったメリットも期待できます。
しかしその一方で、現役時代と同等の給与を支払うのが困難(減給しざるを得ない)といった課題もあり、企業としては何とかこの課題を解決したいものです。
実は、企業が高年齢雇用継続給付の申請を行えば、60歳以上65歳未満の社員に対して給付金を支給することができます。つまり、上述した課題をカバーすることができるのです。
そこで今回は、高年齢雇用継続給付の概要や種類、計算方法、申請時の流れについて解説します。あわせて、高齢者雇用に取り組んでいる企業の事例もご紹介しているので、ぜひご覧ください。
発足された背景とともに解説!高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付とは、60歳時点に比べて給与が75%未満に下がった状態で働き続ける、60歳以上65歳未満の社員(一般被保険者)に支給される給付金のことです。詳しくは後述しますが、「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」の2つに分けられます。
高年齢雇用継続給付が発足された背景には、高年齢者雇用安定法が大きく関係しています。
高年齢者雇用安定法とは、簡単にいうと「高齢者が活躍できる環境を整備する法律」のことです。65歳までの高齢者の雇用を確保すると同時に、65〜70歳までの就業機会も確保するため、高年齢者就業確保措置として以下のいずれかの措置を実施する努力義務が新設されました。
| ●70歳までの定年引き上げ ●定年制の廃止 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入 (特殊関係事業主にくわえて、ほかの事業主によるものを含む) ●70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入 ●70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業 b.事業主が委託、出資(資金提供)などする団体が行う社会貢献事業 |
その結果、多くの企業が定年を迎えた社員の雇用を延長する「勤務延長制度」、そして定年を迎えた社員を一度退職扱いにしてから 再雇用する「再雇用制度」を導入 しています。
しかし、そうなると浮き彫りになるのが「社員における収入の問題」です。たとえば、 再雇用をきっかけに社員の職位が下がった場合、企業は給与を下げる必要が出てきますが、そうすると社員の生活に支障が出る可能性があります。ただし、企業としても再雇用した社員に現役時代と大差ない給与を支払うのは困難です。
そこで、高齢の社員における給与減少の影響を和らげるために作られたのが、高年齢雇用継続給付金です。上述した要件を満たせば60歳以上65歳未満の社員に給付金が支給されるため、給与を下げて再雇用したとしても、社員が経済的なダメージを受けづらくなります。
それぞれで支給資格・期間が異なる!高年齢雇用継続給付の種類

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2つがあり、それぞれで支給資格・期間は異なります。
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、再就職手当などの基本手当を受給していない社員を対象とした給付金です。支給資格には以下の3つがあります。
| ●60歳以上65歳未満の一般被保険者であること ●被保険者であった期間が5年以上であること ●60歳時点とそれ以降の給与を比較し、60歳以後の給与(みなし賃金を含む)が60歳時点の75%未満となっていること |
支給期間は「社員が60歳になった月から65歳になる月まで」です。ただし、各暦月の初日から末日まで被保険者でなければならず、もし65歳になる月の半ばで退職した場合には、該当月は給付金が支給されないので覚えておきましょう。
高年齢再就職給付金
高年齢再就職給付金は、再就職手当などの基本手当を受給している方を対象とした給付金です。支給資格には、以下の6つがあります。
| ●基本手当を受給した後、60歳以後に再就職して、再就職後の各月に支払われる給与が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満であること ●60歳以上65歳未満の一般被保険者であること ●基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること ●再就職前日の基本手当の支給残日数が100日以上あること ●1年以上続けて雇用されることが確実だと認められる安定した職業に就いたこと ●同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと |

支給期間は2種類あり、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が 100日以上200日未満のときは「再就職日の翌日から1年が経過する日が属する月まで」となり、200日以上のときは「再就職日の翌日から2年が経過する日が属する月まで」です。
ただし、被保険者である社員が65歳になった場合は、その期間にかかわらず65歳に達した月までとなるので注意しましょう。
高齢者雇用のために覚えよう!高年齢雇用継続給付の計算方法
高年齢雇用継続給付の支給額は、「60歳時点の給与(月額)」と比較した「支給対象月に支払われた給与」の低下率に応じた支給率を、支給対象月に支払われた給与に乗ずることで算出できます。計算式で表すと「支給率 × 支給対象月に支払われた給与 × 1/100」となります。
なお、低下率は「支給対象月に支払われた給与 ÷ 60歳到達時の給与(月額)×100」で計算します。低下率に応じた支給率は、厚生労働省が発表している「高年齢雇用継続給付の給付金早見表」で確認できるので、あわせて以下をご覧ください。
たとえば、60歳時点の給与(月額)が40万円であり、支給対象月に支払われた給与が28万円だった場合、その低下率は70%(28÷40×100=70)です。低下率が70%だと、支給率は4.67%になるので、高年齢雇用継続給付の支給額は「1万3,076円(4.67×28×1/100=1.3076)」とわかります。

なお、複雑な計算をせずとも厚生労働省が発表している「「支給率早見表」と「支給額早見表」」で概算することも可能です。こちらもぜひご活用ください。
社員ではなく企業が行う!高年齢雇用継続給付の申請の流れ

高年齢雇用継続給付の申請は、基本的に社員本人ではなく、社員を雇用する企業が行います。そのため、申請の流れも把握しておくことが大切です。
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金の初回時における申請の流れは、以下のとおりです。
| 1.社員が企業に対して、受給資格確認票と支給申請書(1回目)を記入し提出する 2.企業がハローワークに、受給資格確認票と支給申請書(1回目)を提出する 3.ハローワークから企業へ、受給資格確認通知書と支給(不支給)決定通知書、支給申請書(2回目)が交付される 4.企業から社員へ、受給資格確認通知書と支給(不支給)決定通知書、支給申請書(2回目)を交付する 5.ハローワークにより支給が受理された場合、社員に給付金が支給される |
なお、2回目以降の申請では受給資格確認手続きが不要になります。
高年齢再就職給付
高年齢再就職給付の初回時における申請の流れは、以下のとおりです。
| 1.社員が企業に対して、受給資格確認票と支給申請書(1回目)を記入し提出する 2.企業がハローワークに、受給資格確認票と支給申請書(1回目)を提出する 3.ハローワークから企業へ、受給資格確認通知書と支給申請書が交付される 4.企業が社員へ、受給資格確認通知書と支給申請書を交付する 5.社員が企業に対して、支給申請書を記入し提出する 6.企業がハローワークに支給申請書を提出する 7.ハローワークから企業へ、支給(不支給)決定通知書と支給申請書(次回分)が交付される 8.企業が社員へ、支給(不支給)決定通知書と支給申請書(次回分)を交付する 9.ハローワークにより支給が受理された場合、社員に給付金が支給される |
なお、高年齢再就職給付の申請においても、2回目以降は受給資格確認手続きが不要になります。
具体的にどんな取り組みをしている?高齢者雇用の事例
高年齢雇用継続給付を申請するには、まず自社にて高齢者雇用を実現させなければなりません。
では、高齢者雇用のため企業はどのような取り組みを行っているのでしょうか。以下で、2つの事例をご紹介します。
株式会社アイ・エス・エス
株式会社アイ・エス・エスが高齢者雇用に着目したきっかけは「技術の強化」であり、さまざまな経験を積んだ方を年齢に関係なく採用したいと考えたそうです。
そこで、東京都の取り組みである「東京キャリア・トライアル65」を通して、新たに高齢者を雇用しました。その結果、タスクオーバーしていた総務業務をサポートしてもらうことができたと同時に、社内のロールモデルとしてほかの社員によい影響を与えられているそうです。
参照:ホワイトカラー系での高齢者雇用の活用事例集|東京都産業労働局
佐藤繊維株式会社
佐藤繊維株式会社において、熟練した確かな技術および知識の維持を支えているのは、主に中高年以上の社員でした。そのため、定年によって中高年以上の社員が退職すると知識・技術の引き継ぎがスムーズに行えなくなり、事業を継続する上で大きな損失となることを懸念していました。
この背景から、佐藤繊維株式会社は高齢者雇用に着手し、就業規則に「雇用継続制度」を規定しました。具体的には、定年を迎える社員が再雇用を希望する場合、家庭の状況や健康状態を確認した上で会社と本人が同意したケースに限り、1年間の再雇用契約が締結されます。これにより、技術・知識の引き継ぎが順調に行われ、後継者の育成につながっているそうです。
参照:5.佐藤繊維株式会社(山形県)~熟練した確かな技術で後継者を育成~|独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
まとめ
人材不足の解消や経験・人脈の活用、ダイバーシティの実現など、さまざまなメリットがある 「高齢者雇用」。これを今以上に推進するために は、「高年齢雇用継続給付」について理解を深めておくとよいでしょう。高齢であることや企業の財政難などを理由に、再雇用した社員の給与を引き下げたとしても、この給付金を受給することで社員の生活に支障が出る心配は少なくなります。
高年齢雇用継続給付の申請は社員本人ではなく企業が行わなければならないため、今回ご紹介した内容を確認の上、ぜひ導入してみてください。
また、Thinkings株式会社では採用業務を大幅に効率化する「採用管理システムsonar ATS」を提供しています。「事務作業に追われ、候補者と向き合う時間がない...」とお困りの方は、ぜひ一度資料をご覧ください。
▼導入企業様からはこんなお声をいただいています▼
「採用担当の残業時間が前年より83%減少した」
「まるで採用担当がもう1人増えたみたい」
「最終面接への移行率が60%→90%に増加した」
⇒採用管理システムsonar ATSの資料はこちらから

1,900社以上にご導入された採用管理システム sonar ATSを展開。このお役立ち記事では、採用セミナーレポートやお役立ちコンテンツをはじめ、企業の採用担当者の皆さまに採用に役立つ有益な情報をお届けしています。