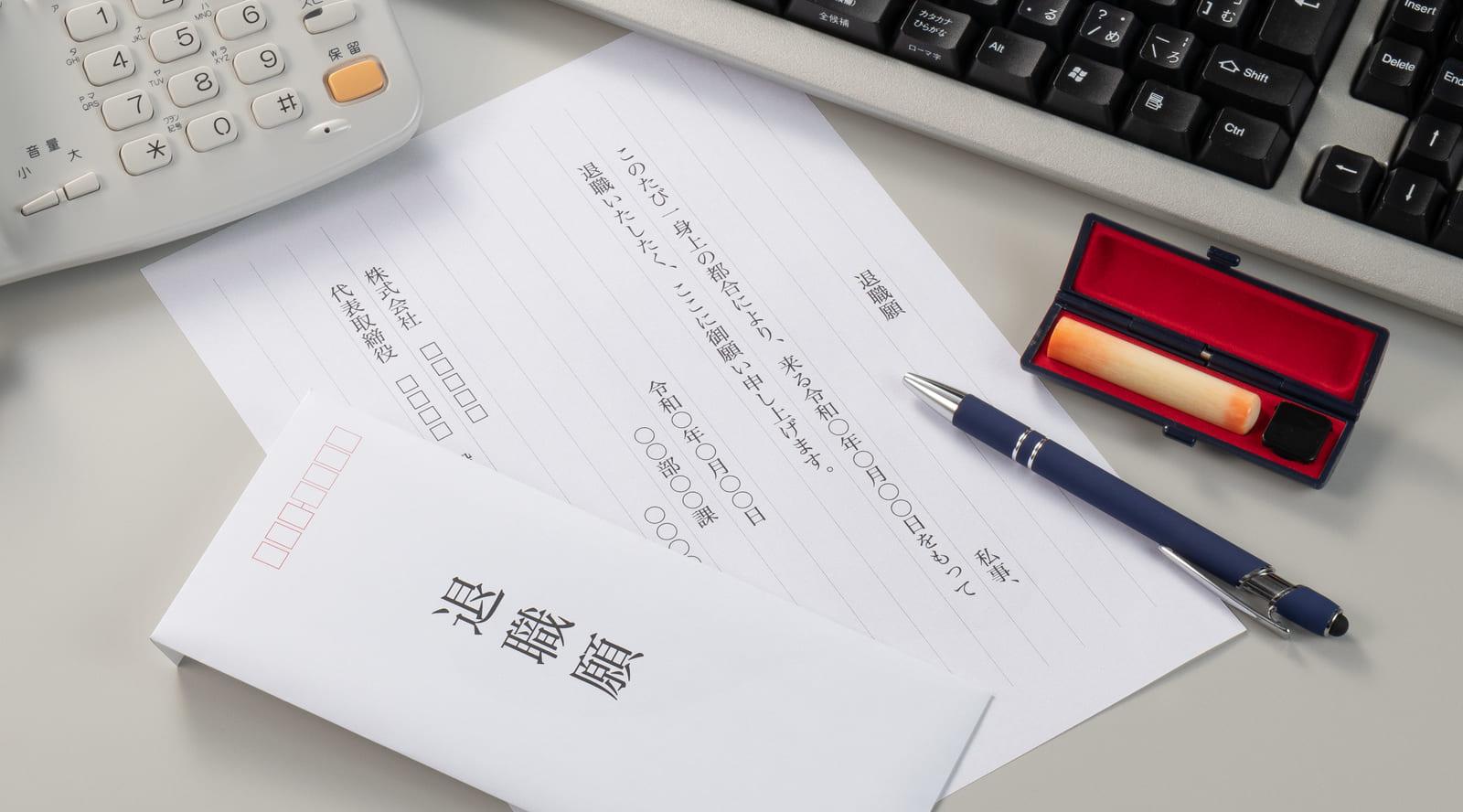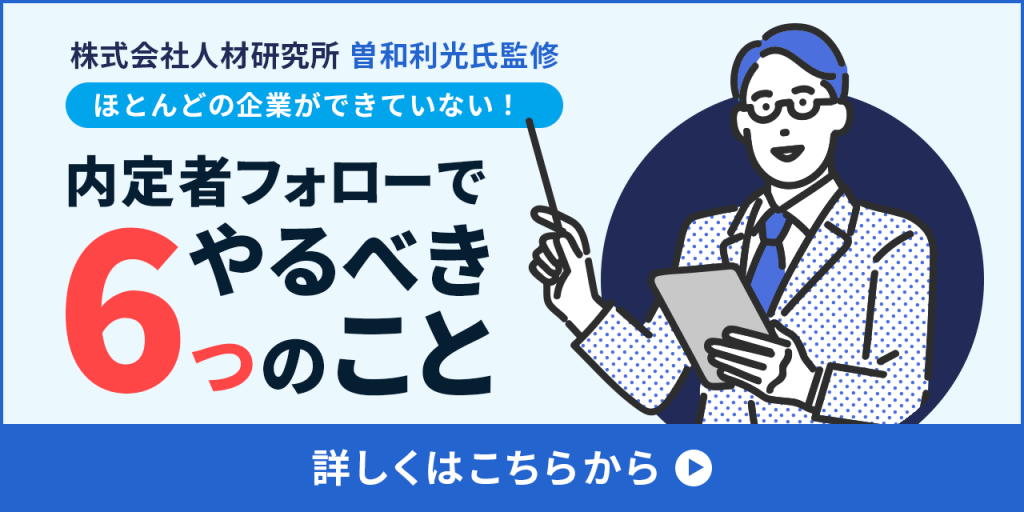お役立ち記事
リフレッシュ休暇を導入!知っておきたいメリット・デメリットと注意点
-
- 人事ノウハウ

「リフレッシュ休暇」という言葉を見聞きしたことはあっても、詳しく理解しておらず、導入すべきか迷っている企業も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、リフレッシュ休暇の概要とともに、導入するメリット・デメリットや注意点について解説します。あわせて、実際にリフレッシュ休暇を導入している企業の事例もご紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
導入企業が増加している!リフレッシュ休暇とは?
リフレッシュ休暇とは、主に「社員の心身の疲労を回復する目的」で付与する休暇のことです。勤続年数に応じて、有給休暇とは別に数日間の休暇を付与します。
厚生労働省が発表している「就労条件総合調査」のデータによると、リフレッシュ休暇がある企業の割合は平成25年度が11.1%、平成30年度が12.4%、平成31年〜令和2年度が13.1%、令和3年度が13.9%となっています。年々少しずつその割合が増えていることから、リフレッシュ休暇を導入する企業は増加傾向にある ことがわかります。
リフレッシュ休暇を導入した場合、社員の生産性の向上が期待できるほか、社員の離職を抑制することにもつながります。そのため、リフレッシュ休暇は企業にとって有益な休暇制度といえるでしょう。
参照:
代表的な特別な休暇制度の例|厚生労働省 働き方・休み方改善ポータルサイト
平成30年就労条件総合調査 結果の概況|厚生労働省
令和2年就労条件総合調査 結果の概況|厚生労働省
令和3年就労条件総合調査 結果の概況|厚生労働省
有給休暇との違い
「リフレッシュ休暇と有給休暇は同じ扱いになる」と認識している方もいるかもしれませんが、これら2つの休暇は似て非なるものです。

リフレッシュ休暇が「法律で定められていない法定外休暇」であるのに対し、有給休暇は「法律で定められた法定休暇」に該当します。そのため、リフレッシュ休暇を導入するか否かは企業ごとに自由に決められますが、有給休暇は企業の義務として導入が定められています。
このほか、リフレッシュ休暇の場合は取得条件や取得日数、給与の支払いの有無などを企業が任意で設定できますが、有給休暇の場合は取得条件や取得日数が法律で定められており、給与に関しては支払わなければなりません。
確認しておこう!リフレッシュ休暇を導入するメリット・デメリット

リフレッシュ休暇の導入には、メリットとデメリットの両方があります。
リフレッシュ休暇のメリット
メリットには、主に以下の3つが挙げられます。
1.社員の生産性が向上する
リフレッシュ休暇を取得した社員は、仕事から離れて心身を休めることができます。そして、心身の疲労を回復させ戻ってきた社員は、仕事へのモチベーションが高まるといわれています。この点から、リフレッシュ休暇の導入には「仕事の生産性が向上する効果」が期待できると考えられます。
また、社員が「次のリフレッシュ休暇のために仕事を頑張ろう」という気持ちになる効果もあるため、モチベーションの維持による生産性の向上も見込めるでしょう。
2.社員の離職を防ぎやすくなる
リフレッシュ休暇を導入した場合、社員の仕事に対するストレスを緩和させやすくなります。なぜなら、リフレッシュ休暇を取得した社員は、数日ほど仕事から離れて自分の好きな時間を過ごすことができるからです。これにより、社員が精神的な苦痛を感じて離職するのを防ぎやすくなります。
また、充実した休暇制度を設けることは、社員の企業への愛着心を高めることにつながるため、この点も離職防止に貢献すると考えられます。
3.企業のイメージアップにつながる
リフレッシュ休暇を導入しており、かつ取得の実績があれば、社会的に「働きやすい環境が整っている企業」というイメージを持たれやすくなり、自社のイメージアップにつながります。
「休日・休暇が多い」「特別休暇が充実している」という点は、人材採用において求職者の興味・関心を惹きやすいポイントです。そのため、リフレッシュ休暇を導入すれば「休暇が充実している企業」と好印象を持ってもらえるようになり、新たな人材を確保しやすくなるでしょう。
リフレッシュ休暇のデメリット
デメリットには、主に以下の2つが挙げられます。
1.業務が滞る可能性がある
一部の社員しかできない業務がある場合、その社員がリフレッシュ休暇を取得した 場合に業務の引き継ぎをうまく行えなくなる可能性があります。最悪の場合、その社員がリフレッシュ休暇を取れなくなることもあるでしょう。また、リフレッシュ休暇中に仕事の連絡をしなければならない可能性もあり、そうなれば本来の目的である「心身の疲労回復」を果たせなくなるかもしれません。
このデメリットを回避するには、リフレッシュ休暇を導入する前に「業務責任の分散」「業務マニュアルの作成」などに取り組み、属人化を解消する必要があります。また、リフレッシュ休暇の運用ルールを明確化して誰もが心身を休められるようにすることも大切です。
2.形だけの休暇制度になる可能性がある
「リフレッシュ休暇があるので各々取得してください」と周知するだけでは社員に浸透せず、なかなか利用してもらえない可能性があります。これでは、社員の心身疲労の回復が難しくなり、ストレスの蓄積や離職につながりかねません。また、リフレッシュ休暇の導入にかかったコストが無駄になってしまう可能性もあります。
このデメリットを回避するには、あらかじめ運用体制を整える必要があります。たとえば、あらかじめ取得時期を決めておくことで、リフレッシュ休暇を取ってもらいやすくなります。
取得のしやすさが鍵!リフレッシュ休暇を導入する際の注意点

リフレッシュ休暇を導入する際は、以下の注意点に留意することも大切です。
ルールを不明瞭にしない
リフレッシュ休暇を導入する際は、ルールを不明瞭にしないよう注意が必要です。もし明確なルールがないまま導入してしまうと、前述したように、形 だけとなってしまう恐れがあります。そのため、リフレッシュ休暇を導入する前に必ずルールを明確にしましょう。
たとえば、取得できる社員の条件には一定の勤続年数を設けている企業が多い傾向があります。具体的には「勤続3年目」「勤続5年目」などです。中には、勤続年数ではなく「休暇中の経験や学びを社員に共有すること」といった課題を条件に設けている企業もあります。
一般的には「勤続3年目は5日間」「勤続7年目は7日間」などと勤続年数に応じて決めている企業が多いので、参考にするとよいでしょう。
こうしたルールを明確にしておけば、社員が計画的にリフレッシュ休暇を利用できるようになるため、形 だけの制度となることを防ぎやすくなります。
「導入したら終わり」と考えない
前述のとおり、リフレッシュ休暇を導入するだけでは社員に利用してもらえない可能性があります。そのため、リフレッシュ休暇を導入したら上司から積極的に休むよう促したり、協力して仕事に取り組む体制を整えたり、それぞれの休暇日を管理し被らないようにしたりすることが大切です。そうすることで、リフレッシュ休暇の導入がより有意義なものになるでしょう。
どれほど効果があるの?リフレッシュ休暇を導入した企業の事例
最後に、リフレッシュ休暇を導入した企業の事例をご紹介します。
アサヒビール株式会社
アサヒビール株式会社は1989年にリフレッシュ休暇を導入し、「連続6日以上の長期休暇を年度始めに申請して取得する」というルールのもと運用しています。現在では、6〜7割の社員がリフレッシュ休暇をはじめとする休暇制度を取得しており、国内・海外旅行を楽しんだり、資格試験の勉強に励んだりと、社員一人ひとりがさまざまな方法で活用しています。
ウシオ電機株式会社
ウシオ電機株式会社では、リフレッシュ休暇の取得を促進するため、取得前年度の2月に人事部から本人と上司にメールで連絡、場合によっては通知書を直接手渡ししています。また、半期経過時にリフレッシュ休暇を取得していない場合は、10月に再び通知しています。こうした取り組みにより、リフレッシュ休暇の利用率は毎年9割以上となっている ようです。
まとめ
リフレッシュ休暇は、社員にとって「仕事から離れて心身を休められる」というメリットがある一方で、企業にとっても「社員の生産性が上がる」「離職を防ぎやすくなる」「自社のイメージアップにつながる」といったメリットがあります。そのため、もしまだ導入していないのであれば、今回ご紹介した注意点に留意しながら取り入れることをおすすめします。
また、Thinkings株式会社では採用業務を大幅に効率化する「採用管理システムsonar ATS」を提供しています。「事務作業に追われ、候補者と向き合う時間がない...」とお困りの方は、ぜひ一度資料をご覧ください。
▼導入企業様からはこんなお声をいただいています▼
「採用担当の残業時間が前年より83%減少した」
「まるで採用担当がもう1人増えたみたい」
「最終面接への移行率が60%→90%に増加した」
⇒採用管理システムsonar ATSの資料はこちらから

1,900社以上にご導入された採用管理システム sonar ATSを展開。このお役立ち記事では、採用セミナーレポートやお役立ちコンテンツをはじめ、企業の採用担当者の皆さまに採用に役立つ有益な情報をお届けしています。