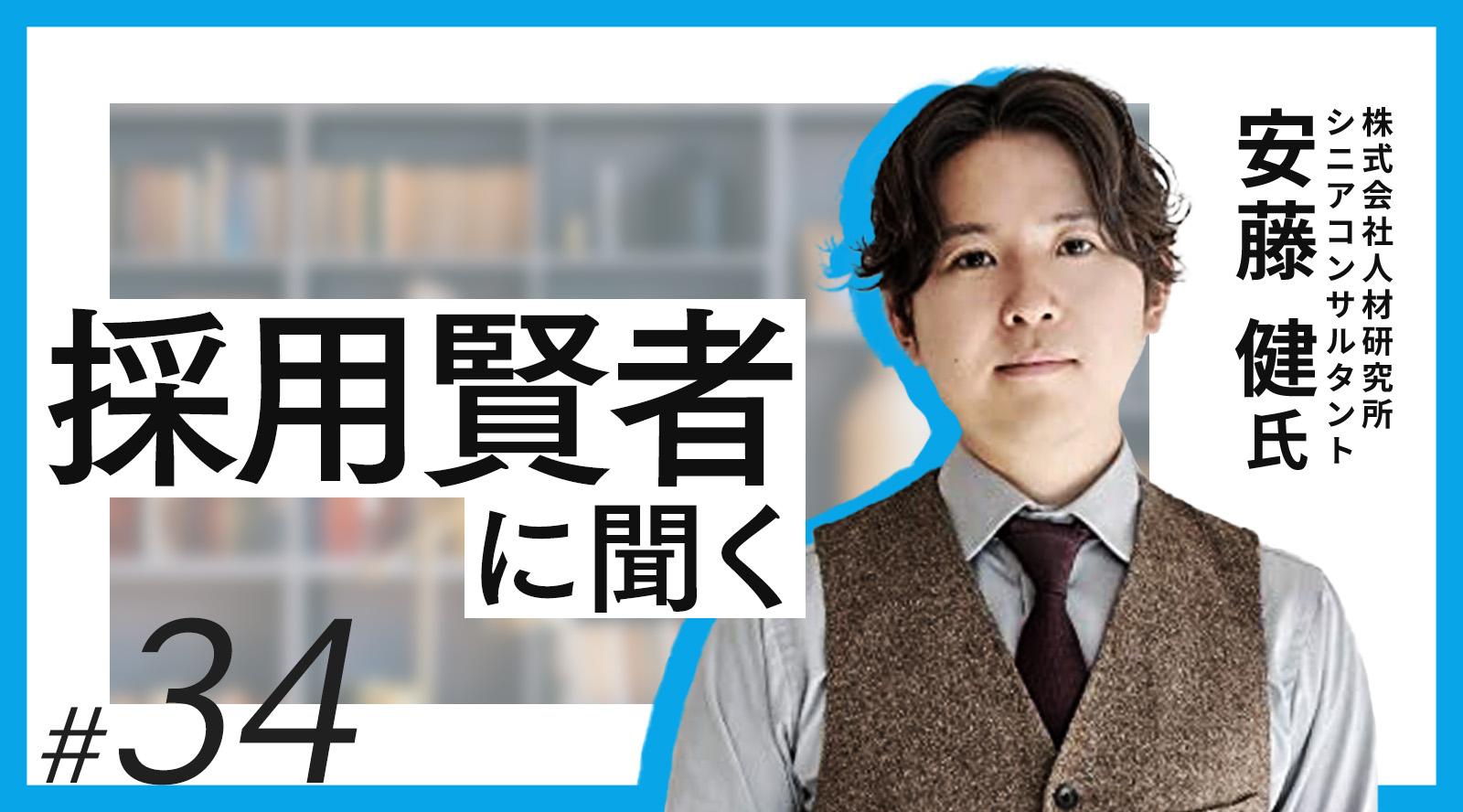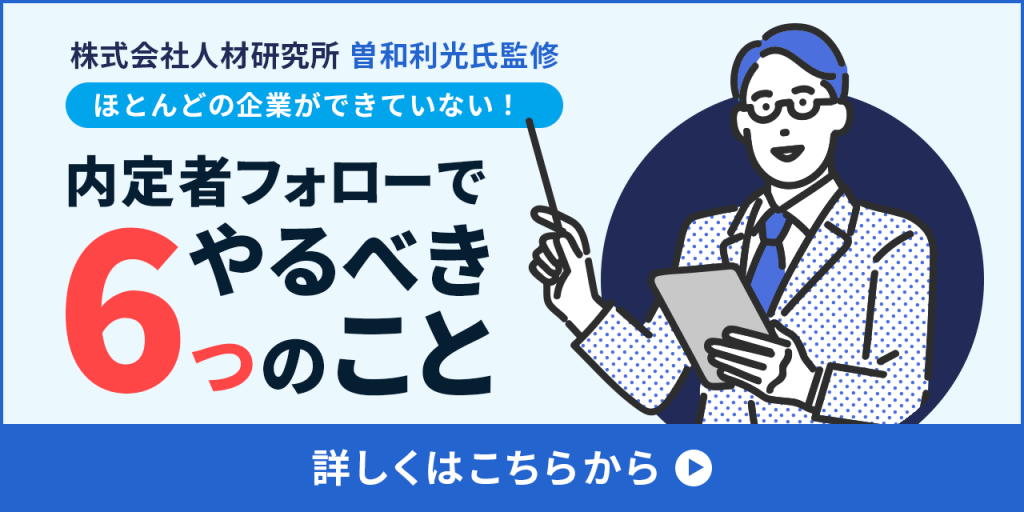お役立ち記事
採用のスペシャリストたちが語る!気持ちを惹きつけ愛着を生む採用テクニック【採用賢者に聞く 第36回】
-
- 専門家コラム

採用の際に学生との距離を縮めるのに大切な要素は、学生を惹きつけて企業または社員に愛着を持ってもらうことです。そのためには、定型のコミュニケーションから少し外れた、ウェットなコミュニケーションが有効な場合があります。
この記事では、 「いまいち学生との距離が縮まらない」「口説くために積極的にコミュニケーションを取りたいけど、自分の方法に自信が持てない」という方に向けて、採用のスペシャリスト4名が実践する独自のコミュニケーションについてご紹介します。
評価者ではなく“支援者”という立場から候補者と向き合う
アチーブメント株式会社 山森拓実さん
評価者ではなく“支援者”という立場から候補者と向き合うアチーブメント株式会社 山森拓実さん

山森拓実 アチーブメント株式会社
人事部(採用育成 / 労務管理・人事制度運用 / 総務)リーダー
京都大学文学部倫理学科卒業。2015年に新卒でアチーブメント株式会社に入社。入社1年目から人事部 新卒採用担当として活動し、年間1万名の学生と最前線で関わる。その後、自身が企画を担当したサマーインターンが、キャリアパーク調べのインターンシップ人気ランキングにて3年連続1位という結果を残した。2020年~2021年の約2年間は、社長室 商品開発チームにて自社の教育プログラムの開発にも取り組む。現在は人事部にて採用、育成、労務、人事制度、総務を担当。Twitterフォロワー数は28,000名を超え、Twitter経由での内定出しも実現。複数メディアに取り上げられる。
まず、採用担当者としてどのような姿勢・意識で候補者と向き合っているかを教えてください。
評価者ではなく「支援者」の立場で、一人の人間として向き合う姿勢が何よりも大切だと考えています。なぜなら、候補者に会社の価値や魅力を一方的に語っても、関係性が深まっていなければ単なる会社自慢になってしまい、候補者を惹きつけることはまずできません。そのため、自社アピールのようなアプローチは極力しないようにしています。
代わりに、徹底して「支援者」として候補者と向き合うことを重要視しています。採用担当者と候補者という立場の違いはありますが、人と人として向き合うこと、候補者が抱える悩みや課題に本気で取り組むことが大切です。支援者として本気で向き合うことで、自然に関係性が深まったり、私という個人を通して会社にも愛着を持ってもらったりできると考えています。
そのうえで、候補者との距離を縮めるためにどのようなコミュニケーション・アクションを実施していますか?
私が候補者とのコミュニケーションで意識しているポイントは以下の4つです。
| ・自己開示をし合える環境作り ・候補者とできるだけ密にコミュニケーションを取る ・細かいフィードバックをして「ちゃんと見ている」ことを伝える ・他社の悪口・陰口は厳禁 |
それぞれのポイントについて以下で解説します。
自己開示をし合える環境作り
弊社では、自分の価値観やビジョンをプレゼンテーションするという選考課題を用意しています。
この課題は候補者数名に社員が加わり、1つのグループで取り組みます。自身の理念やビジョンをグループ内で発表し、お互いにフィードバックをしながら本番までに内容を深めていきます。グループ内で行うフィードバックでは、社員も含めた全員が自分の内面を打ち明け合うため、深いレベルで互いを知れるようになっています。
先ほど支援者のお話をしましたが、急に「私はあなたの支援者だからなんでも話をしてくれ」と言われても、なかなか難しいですよね。なので、どこかで「候補者と採用担当」という垣根を壊し、人と人として向き合うためのきっかけが必要です。この課題には複数の目的がありますが、そのきっかけ作りとしても機能しています。
このような自己開示をし合える環境を作ることで、グループ内で絆のようなものが生まれ、関係性が深まるのはもちろん、「この人たちと働きたい」というような愛着をもってもらいやすくなるのです。

候補者とできるだけ密にコミュニケーションを
接触頻度が減ると、あっという間に関係性が薄くなってしまい愛着も減ってしまいます。関係性を強化するためには、候補者とできるだけ密にコミュニケーションを取る必要があると思います。採用担当者というよりは、人生の先輩や良き相談相手といったポジションを取れていれば、最初よりはカジュアルにコミュニケーションを取れるようになっているはずです。
LINEでも、電話でも、オンライン面談でも、対面でも、連絡手段は問わず、目の前の候補者とコミュニケーションが取りやすい手段で接点を増やす努力をしましょう。
また、コミュニケーションをしているうちに、別の担当者や社員の方との相性が良さそう、または悩みや課題解決に良い影響を与えそうと感じた場合、その時点でその人との接点を作ります。その時々に応じて、候補者のためになると思ったことを柔軟に行うことがとても重要です。
細かいフィードバックをして「ちゃんと見ている」ことを伝える
細かいことですが、相手の良いところや印象を細かく相手にフィードバックするということも大切です。「どこどこのイベントで最初に出会ったよね」「初対面でこういう印象持ったよ」「LINE の返し方がすごく丁寧で印象に残った」など、選考期間中に印象に残っていること・覚えていることを都度伝えてあげるようにしています。
そうすることで、「こんなにも見てくれているんだ」「ちゃんと覚えてくれているんだ」と感じてもらえ、愛着を持っていただきやすくなると思います。
ありがとうございます。最後に密になりすぎることでトラブルに発展したり、関係が薄まってしまうこともあるかと思います。このようなトラブルを防ぐための方法について教えてください。
気持ちのすれ違いや人間関係トラブルを防ぐには
近い距離感でコミュニケーションをとっていく中で気をつけているのは、第一に、「他社を悪く言わない」ことですね。他社を下げて自社を上げるようなやり方をすると、候補者は「この会社はないな」となってしまいます。
もしも特定の他社について言及したいのであれば、「あそこは私も受けたことあるよ。自分がその会社に決めなかった理由はこうだよ」と自分のエピソードとして話し、あくまで「自分はそうだった。でもあなたの場合は違うかもしれないから、1事例として聞いてほしい」という伝え方をしますね。
候補者と深く関わってはいくものの、一線を引くことも大事です。友達や後輩に近い距離感になり、あまりにも深い関係になってしまうと、人間関係のトラブルが起きかねません。
そういった状況を防ぐためにも、候補者とのやりとりをチーム内でブラックボックスにせず、透明性を持って状況を共有・管理をするようにしています。
「こっちが愛するから向こうが愛してくれる」。共通点を探し共感をし合えるコミュニケーションを
株式会社人材研究所 代表取締役 曽和利光さん

曽和 利光
株式会社人材研究所 代表取締役
リクルート人事部ゼネラルマネジャー、ライフネット生命総務部長、オープンハウス組織開発本部長と、人事・採用部門の責任者を務め、主に採用・教育・組織開発の分野で実務やコンサルティングを経験、また多数の就活セミナー・面接対策セミナー講師や情報経営イノベーション専門職大学客員教授も務め、学生向けにも就活関連情報を精力的に発信中。人事歴約20年、これまでに面接した人数は2万人以上。2011年に株式会社人材研究所設立。
まず、採用担当者としてどのような姿勢・意識で候補者と向き合っているかを教えてください。
候補者が自社に愛着を持つようになるのは、「こっちが愛するから向こうが愛してくれる」という順番だと思うんです。候補者が「大事に扱われている」とか「ウェルカムな感じである」「評価されている」といったことを実感できない限りは、採用担当者がどんなことをやったって勝手に愛してくれるなんてことはないと思います。
ですから、候補者に対していかに「あなたのこの部分を当社は評価していますよ。すばらしいと思っていますよ」ということを伝えられるかがポイントだと考えています。
とはいえ、その「褒め」が的外れだったり、本人がそこで売りたいわけではない部分だったりすると、逆効果になりかねません。ですので、徹底して相手のことを聞いて、彼・彼女が「自分は何を生かしていきたいのか」「どこを認めてほしいのか」を深く知ることが大事です。
そのうえで、候補者との距離を縮めるためにどのようなコミュニケーション・アクションを実施していますか?
私が候補者とのコミュニケーションで意識しているポイントは以下の2つです。
| ・本音で話せる関係を構築していくための、共通点探しと自己開示 ・「愛着」のプロセスの最終地点は、「もうええやん作戦」 |
それぞれのポイントについて以下で解説します。
本音で話せる関係を構築していくための、共通点探しと自己開示
候補者のことを深く知るには、「この人だったら本音でいろいろ話しても大丈夫だろう」という感覚を持ってもらう必要があります。
ではそのためにどうするかというと、面接担当者は「候補者と自分はいかに共通点があるか・通ずるものがあるか」を探し、自分の話を交えながら共感をアピールするんです。
「この人なら分かってくれる」という状況を作り出せると、より深い部分まで話が聞けるようになるので、褒めるべきところ・認めるべきところ・評価すべきところがわかってきます。そして、「僕はあなたのことを理解しているし、あなたのこういう部分が素晴らしいと思うから、ぜひ一緒に働いてほしい」と、具体的かつ的確に伝えられるようになります。

「愛着」の最終地点は、「もうええやん作戦」
ここまでのプロセスを経て候補者と密なコミュニケーションが取れる状態になっていて、「自社に対して愛着を持ってもらっているな」と思えたら、最後の最後に取るのは「もうええやん作戦」です(笑)
例えば当社以外にも選考が進んでいる企業があった場合に、「他社と比べてうちのがいいぞ」なんてことを合理的に説明するのは不可能ですよね。
唯一自信を持って言えるのは、「僕は君と一緒に働きたい、うちに入れば活躍できる、それだけが真実だ!」ということ。「だからもうええやん、うちに決めてくれ」と言えるかどうかが、採用担当者としての力量かなと思います。
「合理的にいろいろ考えたら他社の方がいいのかもしれないけど、これだけ求めてくれるんだったら行こうかな」って、それは全然悪いことじゃないと僕は思います。そんなふうに思える企業に出会えることって少ないものです。これも幸せな就活パターンの一つではないでしょうか。
ありがとうございます。最後に関係を深める、愛着を持ってもらうのにやってはいけないことやNG行為はありますか?もしあれば教えてください。
ミスコミュニケーションを防ぐには、手順を踏んで関係を築くことが大事
ミスコミュニケーションにより候補者の気持ちが離れてしまうのを防ぐには、ファクトに基づかない褒め・評価をしないことが重要です。相手のことをきちんと理解していないのに「数撃ちゃ当たる」で褒めたり評価したりするのはやめましょうってことですね。
学生さんからしてみれば、採用担当者や面接官というのは、最初から信頼関係があるわけではなくむしろ疑ってくる存在ですから、そこで褒められたりしても全部眉唾に聞こえてきたりするわけですよね。
ですから、先走らずに、ちゃんとした手順を踏んできちんと関係を築いていくことがトラブル防止というか、関係を深めていくのに重要だと思います。
学生に学びや気づきを提供する。人生のメンターとして学生に寄り添うコミュニケーションを
株式会社PLAN-B 採用担当 宝玉さん

宝玉克彦
株式会社PLAN-B
経営管理部 人事ユニット マネージャー
2017年卒で株式会社PLAN-Bに入社。 一年間セールス職に従事した後、2018年4月から新卒採用担当に。 2019年4月から新卒採用責任者に就任。 2020年4月に子会社立ち上げに伴い出向、事業責任者として人材紹介事業の立ち上げを行う。 2021年1月から人事に復帰、現在まで人事ユニットのマネージャーとして、新卒採用、中途採用、新人育成、組織開発を担当している。
まず、採用担当者としてどのような姿勢・意識で候補者と向き合っているかを教えてください。
一番大切にしているのは、「自社をどう伝えるのか」より先に、「その学生さんにとって、自社が接点を持つことでどんな学びや気づきを感じてもらえるか」「学生さんにとって価値のある時間をどう届けるのか」を考えるということです。
例えば弊社のインターシップでは、会社からの一方的なメッセージではなく、「その学生さんに何を持って帰ってもらうのか」に重きを置いています。インターンシップの前に事前面談を設けて期間中を有意義に過ごすための目標設定を行ったり、インターンシップ参加後は、インターンシップをただの経験ではなく今後に活かせる学び・気づきに変えるための事後面談をさせてもらったりしています。
また、弊社の選考過程では一人ひとりにリクルーターを付けるんですが、リクルーターに対しては、「採用担当ではなく、その学生の就職活動、引いては人生におけるメンターとして就職活動を手伝ってほしい」という話をしているんです。
そして、自社の魅力や特徴を伝える前に、まずは「理想の就活の終わり方って何なんだろう」という部分を明確にしたり、自己分析を通して就職活動のビジョンや軸を作ったり、一緒に考える時間を多く取るようにしています。
そのうえで、候補者との距離を縮めるためにどのようなコミュニケーション・アクションを実施していますか?
私が候補者とのコミュニケーションで意識しているポイントは以下の2つです。
| ・採用担当と学生という垣根を超えたカジュアルなコミュニケーション ・「自分は学生を評価する立場ではない」ことを伝える |
それぞれのポイントについて以下で解説します。

採用担当と学生という垣根を超えたカジュアルなコミュニケーション
企業の採用担当と学生という垣根を越えた、普通の友人や後輩としかしないようなコミュニケーションをとったりもしています。例えば休みの日に一緒にサウナに行ったり、面談時に話していた店に飲みに行ったり。面接時に聞いた悩みに関する記事を後日LINEで送ってあげたりすることもありますね。
これは、会社に対する愛着を持ってもらう前に、担当リクルーター個人に対する「この人尊敬できるな」 「この人信頼できるな」という気持ちをどう獲得するのかが大切だと思っているからです。
このほか、「こちら側も心を開いて自己開示する」という部分も大切にしています。学生さんに自身のことを伝えてもらいたいのであれば、同じぐらい我々も心を開くべきでしょう。
ですので、我々も「何で自分がこの会社を選んで働いているのか」「会社の中でどんなことを実現したいと思って仕事をしているのか」「自分がどういうことを成し遂げたいのか」など、まず自分という人間をきちんと伝えるようにしています。
「自分は学生を評価する立場ではない」ことを伝える
もう一つ必ず行っているのは、「自分は学生を評価する立場ではない」ということを学生さんに伝えることです。もし「インターンシップについたメンターや人事のメンバーが自分を評価している」と思うと、一つの言動や発言にすごく気を使ってしまって本音は言えないものですよね。
会社としても、インターンシップのパフォーマンス評価は運営責任者が行う、リクルーターがついてからの評価も面接官が行うという形で、評価にリクルーターやメンターが一切関わらないようにしています。
「この人は本当に自分を評価しに来ているわけではないんだな」「本当に自分のためを思ってやってくれているんだな」と自然に思っていただくには、そういったシステム的な部分での努力も必要だと考えています。
学生の人生を全力で応援する姿勢が本当の愛着を生む株式会社fanphare(ファンファーレ) 高橋麻菜美さん

株式会社fanphare(ファンファーレ) 高橋麻菜美
新卒でホテル業界にて法人営業を務め、 その後、キヤノンのグループ会社での人材開発、ウエディング大手であるノバレーゼとキャリアを重ね、人事採用に携わり、人材開発部長へ就任。 その後、リクルートのグローバル人材事業であるRGFにて、ヘッドハンター・コンサルタントのマネージャーを経験。 2020年に株式会社fanphareを共同経営者として起業。人材紹介、採用コンサルティング、スポーツメディアなどを事業として展開する。
まず、採用担当者としてどのような姿勢・意識で候補者と向き合っているかを教えてください。
自社に愛着を持たせるには、自社をよく知ってもらい興味を引くことが必要ですが、学生さんが知りたいポイントは人それぞれです。なのでまずは一人一人の学生のことをよく知ることを意識しています。
そのためには、初回接触の際にどれだけ情報を引き出せるかがポイントになるのかなと思います。
例えば、「この学生は将来経営者になりたいのか」「親御さんも経営者なのか」といった情報を知ることで、「この学生にはこういう話をしてあげよう」という指針を立てることができます。情報をたくさん引き出せば引き出すほど当てられるものが増えていきます。
このときに大事なのは、こちら側も自己開示をして相互コミュニケーションを取ることです。自分のことも開示せずに学生にばかり質問したり、会社の言いたいことだけ伝えたりしたとしても、響かないと思いますね。「自分のことをちゃんと知ってもらった」「自分もこの会社のことをよく知っている」という状態になると、自然と愛着も湧きやすくなると思います。
そのうえで、候補者との距離を縮めるためにどのようなコミュニケーション・アクションを実施していますか?
私が候補者とのコミュニケーションで意識しているポイントは以下の3つです。
| ・愛着を持ってもらうには、単純に接触回数を増やすのが効果的 ・不合格者へのコミュニケーションも重要 ・最後の一押しができないときは、口説き落とせない理由を探って対応する |
それぞれのポイントについて以下で解説します。
愛着を持ってもらうには、単純に接触回数を増やすのが効果的
候補者に自社への愛着を持たせるポイントは、まず単純に接触回数だと思います。友達でも何回も会った人の方が理解し合えるし愛着が湧くのと同じで、接触回数が多いほど会社や採用担当者に対して信頼を持ちやすくなりますし、「僕は・私は何でこの会社を受けているのか」という志望動機形成をじっくり一緒に高められます。
また、「自分のことも理解してもらえている」と自然と思えるものです。
採用で結果が出ている会社さんの特徴として、少なくとも5回、多いところだと10回は接触のタッチポイントを設けています。接触回数を増やせるかどうか、そしてその時々で適切な人物を接触させ、学生にとって有意義な時間を送らせているかどうかが重要です。
人事担当でもいいし現場の人でもいいと思いますが、このバリエーションが豊富なほどいいですね。多くの人と接触することで会社の理解も進みますし、「この人が上司になるんだ」「現場はこんな感じなんだ」というような具体的にイメージができればできるほど、志望動機は高まりやすくなります。

不合格者へのコミュニケーションも重要
採用活動というのは全てを通してファンマーケティングだと思いますので、翌年・翌々年と永続的なファンマーケティングを考えると、「採りたい学生だけでなく、あらゆる人に対して満足度が高まるような選考設計をしているか」をまずは考えることが重要です。
どうしても「確度が高い学生・採りたい学生に対する愛着」に意識が集中しがちですが、応募してきた全員が潜在顧客であり全員がクチコミ投稿者ですから、「不合格者の方に対しても、どういった対応をしているのか」も非常に大事だと思います。
不合格者の方には連絡をしていない企業もあると思いますが、「見つけてくれてありがとうございました」といった連絡をするべきだと思いますし、二次面接までいってくれた人たちに対してはフィードバックも込みできちんと理由を伝えるべきだと思います。
それをすることで、恩義に感じ、「私はダメだったけど、いい会社だった。あなたには向いているんじゃないか」と、良いクチコミが広がっていくことも多々あります。
また、通過者の方や内定者の方も、「きちんと対応してくれるあの会社の内定者になれた」とか「自分は最終面接に進んでいる」と誇りに思え、会社のブランド価値が高まっていきます。
最後の一押しができないときは、口説き落とせない理由を探って対応する
「会社としてはその学生さんが欲しくて、相手もうちを好きだと言ってくれている、けれど他に本命の企業があってなかなか口説き落とせない」というような状況も往々にしてあると思います。
そういった場合は、決めきれないポイントがどこにあるのかをしっかりと把握し理解することが大事です。「情報が足りていなくて順番が変わらないのか」、もしくは「情報は十分にあるけれど、本人の気持ちの問題なのか」をまず探ります。その上でテコ入れができそうであればしますし、「これは考えさせたほうがいいな」という場合にはあえて距離を置くことも一つ重要な手段だと思います。
そもそも今すぐ決められる人って本当に一握りなんですよね。時間が必要な人もいると思いますし、自分の中での内省が必要な人・背中を押して欲しい人もいると思いますので、そこはパーソナリティーを見てジャッジして行動してあげることが大事ですね。
ありがとうございます。最後に、ご自身の経験の中で印象的な学生とのエピソードはありますか?もしあれば教えてください。
採用できなくても本気の向き合いは無駄にならない
以前ウエディング会社にいた時の話なのですが、「本当に入社してほしいな」と感じた学生がいました。しかしその学生には別の夢があり、その夢にチャレンジするかうちに入社するかですごく悩んでいたんです。
そのとき私たちは「今無理に説得しても、相手のためにならないだろう」と判断し、「思いっきりチャレンジしてこい!」というようなことを言って送り出しました。そして結局その学生は夢を叶え、その世界で大きな活躍をしたんです。
私たちが真摯に向き合ったからなのか、それで私たちの関係は終わりではなく、その後も何かあるたびに連絡をくれたり良いお付き合いが続いて、就活中の後輩に私たちの会社を紹介してくれたりもしました。
さらに、自身が結婚するときには、「実は結婚するならここと決めていた」と言って当時働いていたウエディング会社を利用してくれたんです。長い期間を経て戻ってきてくれた感じがして本当に嬉しかったですし、採用することは叶わなかったけれどもそれ以上のものを返してもらいました。
採用活動というのは「採用すること」が目的ではありますが、学生の人生を全力で応援することこそが、本当の意味での愛着をもたらすのだと思います。
まとめ
今回は、各社の採用担当者の皆さんに、採用活動で自社に学生を惹きつけ愛着を抱いてもらうためのコミュニケーションやアクションについてお話いただきました。各採用担当者さんそれぞれ独自のテクニックをお持ちでしたが、全員が重要視していたのは以下の3点です。
・自社に採用することだけを考えるのではなく、学生さんの人生に真摯に向き合うこと
・自社をアピールすることより、自分たちが学生に何を与えられるかを重視すること
・自己開示によって内面を打ち明け合い、採用担当と学生という垣根を超えた関係を作ること
学生さんとの距離の縮め方・自社に愛着を持ってもらう方法にお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
また、Thinkings株式会社では採用業務を大幅に効率化する「採用管理システムsonar ATS」を提供しています。「事務作業に追われ、候補者と向き合う時間がない...」とお困りの方は、ぜひ一度資料をご覧ください。
▼導入企業様からはこんなお声をいただいています▼
「採用担当の残業時間が前年より83%減少した」
「まるで採用担当がもう1人増えたみたい」
「最終面接への移行率が60%→90%に増加した」
⇒採用管理システムsonar ATSの資料はこちらから

1,900社以上にご導入された採用管理システム sonar ATSを展開。このお役立ち記事では、採用セミナーレポートやお役立ちコンテンツをはじめ、企業の採用担当者の皆さまに採用に役立つ有益な情報をお届けしています。