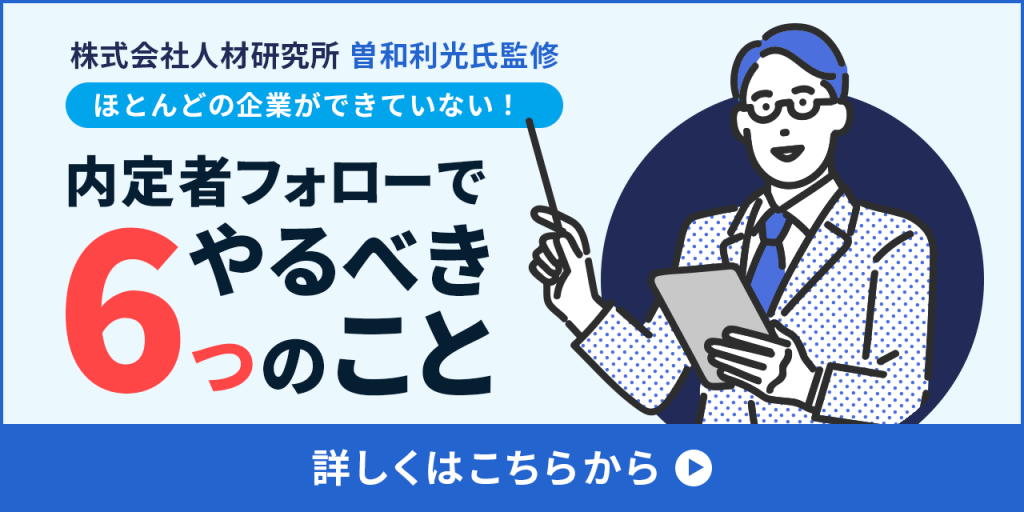お役立ち記事
失敗・成功事例も検証!冬の短期オンラインインターンシップの作り方【採用賢者に聞く 第34回】
-
- 専門家コラム
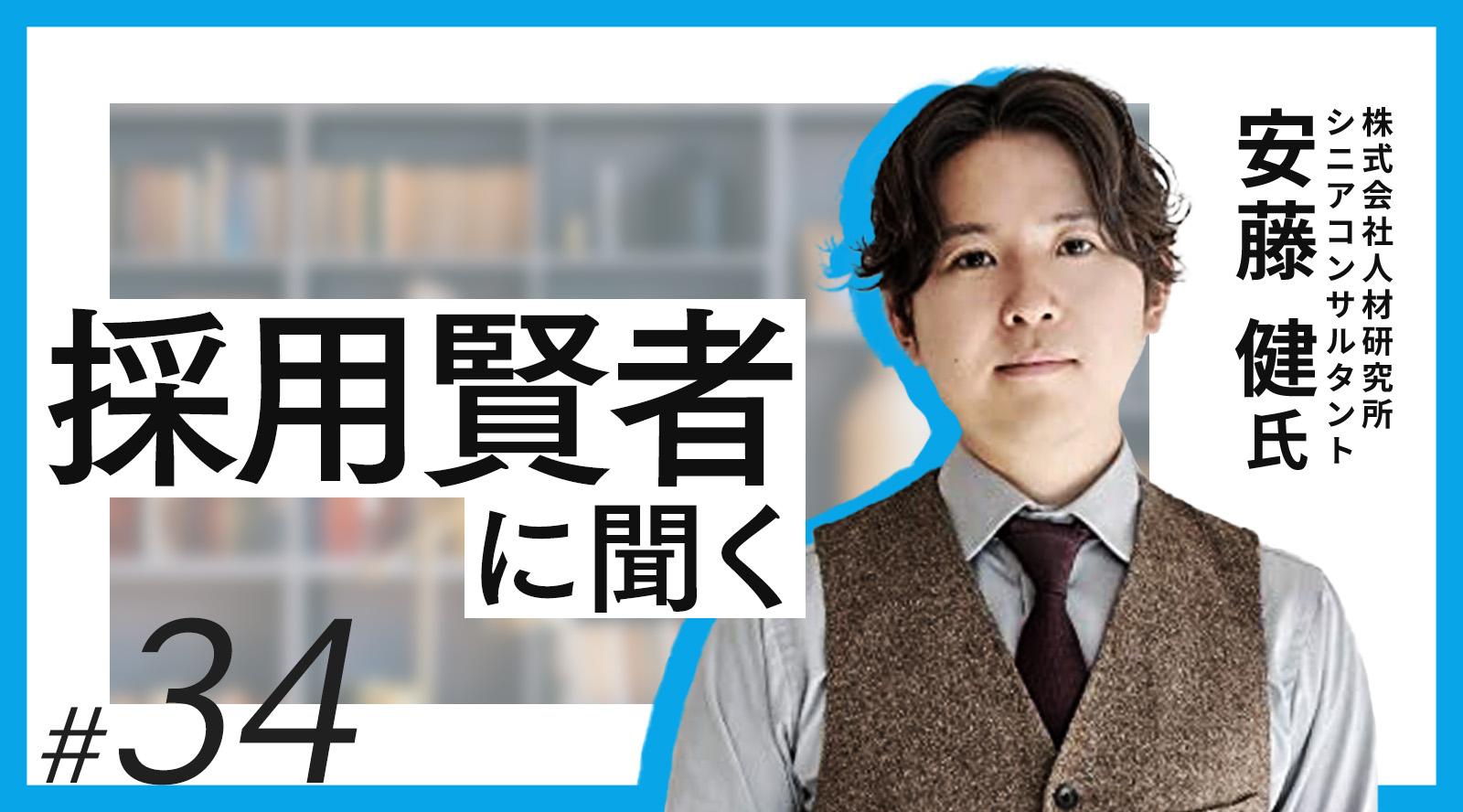
オンラインインターンシップは、コロナ禍の行動自粛によって生まれた新しいインターンシップの方法です。リアルでのインターンシップの開催が難しくなったことにより、この冬にオンラインでの開催を検討している採用担当者の方も多いのではないでしょうか。
今回は、短期間で行うオンラインインターンシップの要点を、株式会社人材研究所のシニアコンサルタント・安藤健氏に解説いただきます。失敗・成功事例なども交え、通常のインターンシップとの違いやオンラインインターンシップの設計・実施のポイント、失敗しないための要点を押さえていきましょう。
1dayでも、即効性を求められる冬のインターンシップ

冬によく実施される短期オンラインインターンシップについて、その特徴を教えてください。
まずは期間についてお話しします。インターンシップ(以下、IS)は、以下のように「1day」「複数days」「長期」の3つに分けられます。
| 【インターンシップの期間】 ・1day ……… 1日 ・複数days … 概ね2~3日。最大5営業日ぐらい。 ・長期 ……… 1カ月~1年 |
このうち、短期ISは、1dayのISを指すのが一般的です。1日の日程で、だいたい3~6時間のプログラムで実施されます。
オンラインで実施する IS の大きな特徴は、学生が自宅から参加できるという点に尽きるでしょう。移動時間もかからず、手軽に参加できるメリットがあります。開催する企業側も、会場を押さえる必要がなく、学生の交通費を負担している企業にとっては、コストも抑えることができます。
また、空間に制限がないので、たくさんの学生に参加してもらうことも可能です。なお、オンライン ISに使用されるWeb会議システムとしては、「Zoom」や「Teams」が主流だと思います。まとめると、短期オンラインISは、1日の日程で、全国各地の学生を効率的に集客できる施策と言えます。
冬のISという、時期的な特徴も教えてください。
近年、学生の就活は二極化しています。この時期は、夏からいち早く就活を続けてきた学生と、まだ準備もこれからという学生が混在していると考えられます。そして後者には、夏は忙しくて全然動けなかったという体育会系の学生や、理系院生も含まれているはずです。早期から動いている学生をきちんとフォローしつつも、これから就活を本格化させる学生の駆け込み需要を取りこぼさないことが、チャンスの拡大につながると考えられます。
そのため、「冬のISに力を入れる企業は増えている傾向にある」というのが私の印象です。
もう一つ、抑えておきたいのは、冬のISのすぐ直後には、本選考が始まるということです。そのため、本選考につながるように、学生に“動機づけ”することがここでの目指すべきゴールと言えます。それを念頭に置いて、コンテンツをしっかり吟味することが、非常に重要なポイントになるでしょう。
具体的に、冬の短期ISの場合、どのようなコンテンツが望ましいと考えていますか?
IS のコンテンツは、次の2つに分類できます。一つめの「仕事疑似体験型」は、実際の部署やプロジェクトに配置して、就業体験してもらうというものです。もう一つの「特別プログラム型」は、ケーススタディやワークなどを通じて、仕事について理解を深めるコンテンツです。
冬に実施されることの多い短期ISの場合、後者の「特別プログラム型」がおすすめです。狙った成果が得やすく、60分で会社説明、60分でワーク、その後の座談会など、構造化しやすいことが一番の理由です。
一方、就業体験がメインの「仕事疑似体験型」は、まさにリアルな職場を伝えられますが、長期でなければ成果を得にくいのが特徴です。さらに、ある学生にとっては「仕事内容の理解」、ある学生にとっては「先輩社員の魅力」というように、成果の受け取り方が学生個人に委ねられます。フレキシブル・ゴールとなってしまうため、短期ISの場合、中途半端な成果に終わる可能性が高いと考えられます。
| ISコンテンツ別メリット・デメリット ■仕事疑似体験型 【○】仕事をリアルに体感できる。 【×】何を成果として得るかは、学生次第。現場の負担・混乱も大きい。 ■特別プログラム型 【○】伝えたい情報を効率的にインプットでき、学生の達成感も高い。 【×】リアリティや職場の雰囲気の実感は、就業体験より劣る。 |
オンラインの活用法で分かれた、失敗と成功

今までご相談を受けた中で、冬の短期オンラインISにおける失敗事例と成功事例を教えていただけますか?
オンラインISにおいては、オンラインならではの施策が必要だと感じた事例を、それぞれご紹介します。
| <失敗事例> オンラインにも関わらず、オフラインと同様のコンテンツを提供 東京の下町のある専門商社の例です。ここ10年の間、新卒採用をストップしていましたが、近年のコロナショックの反動で業績アップ。増員が必要となり、久しぶりに新卒採用を再開し、初めてオンラインISを実施することになりました。しかし、IS参加者20名のうち、本選考に臨んでくれたのはわずか3名のみで、期待を大きく下回る結果になりました。 [敗因1]一方的な会社説明が2時間続いたこと 同社は、10年前に対面で実施したISのコンテンツを、そのままオンラインで実施していました。コンテンツは2部構成となっていて、前半は社長講話60分と、人事担当者からの業界・会社・仕事についての説明60分というもの。つまり、学生はまるまる2時間、PCの前で一方的な話を聞くだけの状態だったのです。話を2時間聞き続けることは、オフラインだとその場の空気感や熱意も伝わりやすいため耐えられるのですが、オンラインではかなりの集中を強いられます。そのため、参加した学生はすっかり疲れてしまい、動機づけに結びつかなかったと考えられます。 [敗因2]質疑応答は社員1に対して学生20で、密な交流ができなかったこと 2部構成の後半は、先輩社員への質疑応答でした。この企画自体はインタラクティブで相互に交流できるので、よかったと思います。問題は、質問に応じる先輩社員がたった一人だということです。しかも、参加者20名が全員同じルームに括られていました。学生は周りの学生の反応を見計らうため質問するチャンスも量も少なく、十分に満足できなかったと予想されます。 |
| <成功事例> 関係性を深める、インタラクティブなコンテンツとして活用 ある大阪の食品メーカーのISでは、小グループに分かれて社員と共同で120分のワークに取り組み、最後に成果を発表。内容としては一般的な特別プログラム型のコンテンツですが、そこには“動機づけ”につながる仕掛けがあったのです。その結果、IS参加者の約60%が本選考に応募するという結果になりました。 [勝因1]サポーターではなく、メンバーとして社員もワークに参加したこと ワークを実施する際、各グループには協力社員が配置されたのですが、サポーター的な立場ではなく、同じワークに取り組むメンバーとして参加しました。ともにワークに臨み、発表まで一緒に取り組むことで、学生との関係性を構築。それが動機づけに大きく貢献したと考えられます。 [勝因2]フォローは人事担当ではなく、関係性を築いた社員から 一般的なISでは、最後に人事担当者が出てきて、次回のイベントや採用スケジュールの連絡などを行います。しかし、この企業はその連絡も、その後の学生のフォローも、同じグループの協力社員が直接対応しました。すでに関係性のある協力社員からのアプローチのため、学生への強い動機づけにつながり、本選考への応募に大きく貢献したと推測されます。 |
「冬×短期×オンライン」で押さえたいISのポイント

それぞれの事例から見える冬の短期オンラインISのポイントは、どのようなものでしょうか?
ポイントをまとめると次のようになります。
■インタラクティブなコンテンツを意識
一方的な情報提供は、学生に非常に負荷がかかり、結果としてマイナスイメージにつながる恐れがあります。相互に交流できるコンテンツを用意し、学生の集中力を切らせない工夫を講じたほうがよいでしょう。
■五感に訴えられないぶん、情報を密にする
オンラインのISは、視覚と聴覚にしか訴えることができません。そのぶん学生に与える印象が薄くなります。それを補うには、情報量を増やすことが必要です。たとえば、一枚だけのスライドよりも、ワンセンテンスでどんどんスライドが変わる、文字やグラフが動くなど、視覚効果を入れると、視覚的な情報量が多くなり、学生の印象も深まるはずです。
■できるだけ個別に対応する
オンラインISは、スペースの制限がないため、大人数の学生に一度に参加してもらうことができます。しかし、その場合でも、4~5名程度の小グループで分け、それぞれに担当社員を付けたほうがベターです。そのほうが、一人あたりのワークの作業量、質問量が増え、体験をリッチにすることができます。これは、前項の“情報を密にする”という観点からも重要です。
■“動機づけ”を目指し、まずは“関係づくり”を
冬のISは、本選考が目前に迫っているので、「まずは会社のことをしっかり知ってもいたい!」という気持ちはわかります。しかし、本選考につなげるためには、学生の“動機づけ”が最も重要です。そのためには、学生としっかり関係性をつくらなくてなりません。関係性ができているからこそ伝わる魅力や、関係性そのものが魅力となる場合もあるので、ポイントとして押さえてほしいと思います。
冬のISは、新たな学生と出会える最後のコンテンツ

最後に、冬の短期オンラインISに臨む採用担当者に、改めてその重要性を教えてください。
冬のISは、本選考前の採用担当者にとって非常に忙しい時期であり、取り組むのは簡単なことではありません。しかし、「冬のISは、志望度が上がりきってはいないけれど、興味はある」という学生が、気軽に参加してくれる最後のコンテンツとなります。ここで接点を持たなければ、来てくれなかった学生と出会えるチャンスを逃してしまうことになるので、ぜひ力を入れていただければと思います。
また、冬のISは、夏のISで接点を持った学生と、関係性を再び強くするチャンスでもあります。特別なコンテンツを用意しなくても、個別に「夏にも参加してくれたよね?」などと事前にコミュニケーションをとり、IS後も感想を聞くなどのアフターフォローをするだけで、“動機づけ”につながりやすくなります。夏からの積み重ねが功を奏するように、冬のISのタイミングを活用し、学生たちと丁寧に接して、採用成功につなげてください。
また、Thinkings株式会社では採用業務を大幅に効率化する「採用管理システムsonar ATS」を提供しています。「事務作業に追われ、候補者と向き合う時間がない...」とお困りの方は、ぜひ一度資料をご覧ください。
▼導入企業様からはこんなお声をいただいています▼
「採用担当の残業時間が前年より83%減少した」
「まるで採用担当がもう1人増えたみたい」
「最終面接への移行率が60%→90%に増加した」
⇒採用管理システムsonar ATSの資料はこちらから