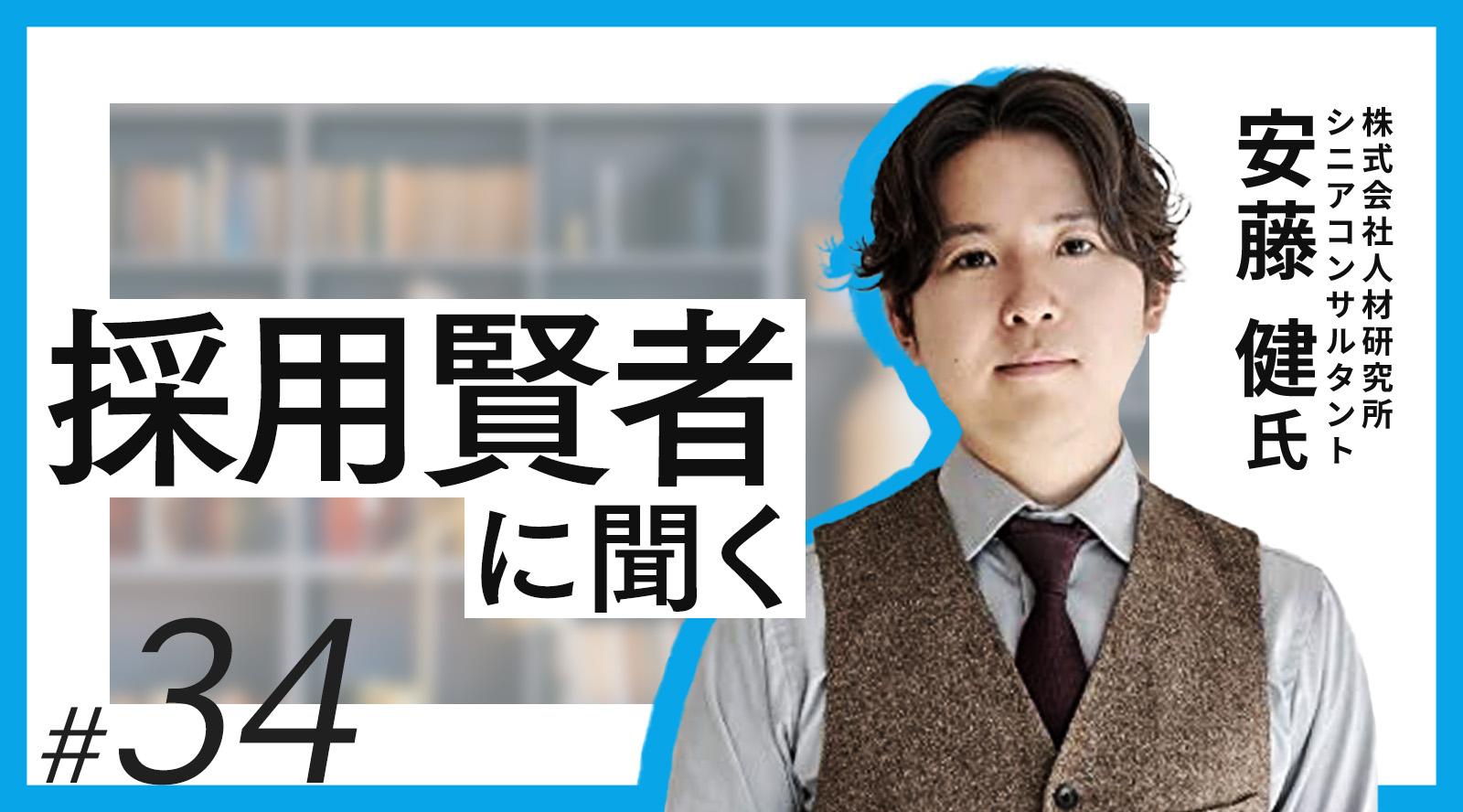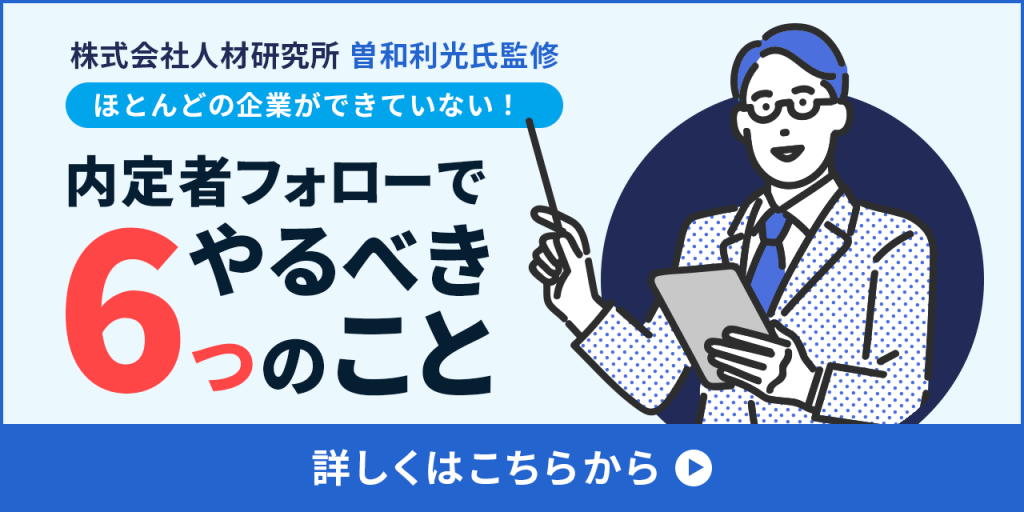お役立ち記事
採用ナビはもう古い?採用担当者が知っておきたい採用手法と取り入れ方【採用賢者に聞く 第15回】
-
- 専門家コラム

社会が多様化する中で、企業が求める人材も同じように多様化しています。その流れと歩調を合わせるように、さまざまな採用手法が出現し、以前は主流だった採用ナビに頼る手法が時代遅れになりつつあります。昨今、ナビ以外の手法が注目を集めている理由や他にどのような手法があるのかなど、企業の採用力強化をサポートするジャンプ株式会社の増渕知行氏に伺いました。
閉じられていた採用の門戸を採用ナビが開いた

――採用ナビが成立した背景はどのようなものだったのでしょう。
1996年にリクナビがWebサービスを開始。それに続く形で、1999年にはマイナビがサービスを開始しました。これらのサービスが開始する前は、学生は紙媒体だけで就活をしていたんです。分厚い情報誌が自宅に届き、付属の資料請求はがきを送るとパンフレットが送られてくる。説明会の予約もはがきでしていました。大学のランクによって企業から届く情報量に差があったり、エントリーできる企業が限られていたりしたんです。そういった格差を是正し、就活に自由競争の概念を浸透させたのが採用ナビです。
――インターネットが普及しつつあった時代というのも関係ありそうですね。
そうですね。ちょうどPCが普及し、インターネットの黎明期ということもあって採用ナビを使うのが当たり前になっていきました。学生は採用ナビに登録してから興味のある企業にエントリーし、企業はエントリーした学生の中から人材を選んでいくというひとつの仕組みがつくられたのです。2000年代前半は、まさに採用ナビ全盛期と言えるでしょう。
リーマンショックがきっかけとなった脱ナビ採用の流れ

――最近、その流れが変わったということなのでしょうか。
いいえ、だいぶ前からですね。2008年に起こったリーマンショックが大きなターニングポイントです。企業が採用を控えるようになり、求人倍率が落ち、採用にかける予算が一気に削減されました。そのため、採用の方法を変えなければならなくなりました。これまでのように、採用ナビを利用してたくさんの学生を集めて、振り落とすという手法ではなく、より低予算でマッチング度の高い学生を集める動きが出てきたんです。それが現在の採用手法の多様化につながっています。
――今、採用ナビの立ち位置はどうなっているのでしょうか。
採用ナビを使っていない学生はほとんどいません。しかし、同時に採用ナビしか使わない学生も皆無です。現在の学生はSNSや就活アプリを使って莫大な情報量を得ていますし、その上で情報を取捨選択する能力にも長けています。そういった背景から、採用ナビだけで就活を行っている学生はいなくなっています。
――企業にとって採用ナビはどのような存在になっているのでしょう。
企業にとっても脱ナビ採用というトレンドは確固たるものになっています。先述したようにリーマンショックが契機になり、さまざまな採用手法が出現しました。ダイレクトリクルーティングやマッチングイベント、マッチングアプリなどがそうです。また、HRテックといわれるIT系の企業が参入してきたこともその流れに拍車をかけました。
ただ、学生と同様に、採用ナビをまったく利用しないという企業はまだ少数派です。やはり多くの学生が見るメディアであることは確かですから、マスを抑えるという意味で採用ナビを利用している企業は多いですね。ダイレクトリクルーティングや特化型の戦略を打ちつつ、後半戦に向けての保険として採用ナビを最低限掲載しておく、という企業が増えているように感じます。
「リアルとWeb」「1人と多数」ケースによって組み替える採用手法

――採用ナビ以外の採用手法として、どのようなものが挙げられますか。
採用手法を分解すると、「1対1×リアル」「1対多数×リアル」「1対1×Web」「1対多数×Web」という4つに分類できます。それぞれの手法についてご説明します。
 ▲採用手法の4分類イメージ図
▲採用手法の4分類イメージ図【1対多数×リアル】
| ●マッチングイベント 主に特定の学生を集めて企業との出会いを創出するイベントが主流です。上位校の学生や地方学生、体育会系、ベンチャー志向といった学生を集めたマッチングイベントが開かれています。 ●キャンパスリクルーティング 特に理系の学生に有効な手法です。理系学生は研究室のつながりが強い傾向があるので、採用した学生と一緒に研究室に挨拶に行くといった手法も有効になります。 |
【1対多数×Web】
| ●SNS 学生はTwitterやInstagram、LINEを利用して興味ある企業の追加情報を収集することが多い傾向にあります。SNSをうまく利用している企業であれば、母集団形成にうまくつなげている例もあります。 ●特化型ナビ 上位校の学生や地方学生、体育会系、ベンチャー志向といった、あるカテゴリに特化した形で学生を集めている採用ナビも増えています。採用したい人物像が明確な企業が利用していることが多いです。 |
【1対1×リアル】
| ●新卒紹介 新卒紹介を得意とするベンダーも増加傾向にあります。中途採用よりも特定期間に大量の学生が動くため、新規参入でも集客しやすいのです。以前であれば就活で苦戦した学生が後半で利用していましたが、年々利用の早期化が進んでいます。 ●リファラル 新卒採用で社員紹介が機能するのは、内定者および入社一年目の社員までですね。それ以前となると、後輩とのグリップが弱くなります。企業によっては、内定者に後輩のインターン集客を目標設定して取り組ませているところもあります。 |
【1対1×Web】
| ●ダイレクトリクルーティングツール 今一番伸びているのがダイレクトリクルーティングです。コロナの影響もあり、合同説明会が激減した影響で、学生は良い企業と偶然出会うチャンスが減りました。結果、偶然の出会いを生み出しているのがダイレクトリクルーティングです。知らない企業からオファーが届いたら、調べてインターンシップに参加するという学生が増えているのです。 ●OBマッチングアプリ OB・OGと出会えるマッチングアプリも伸びています。学生は企業のリアルな情報が欲しいと感じていますから、それを聞き出せるOB・OGとの接点はとても貴重です。 |
――このように採用手法が多様化したのはなぜなのでしょうか。
学生自身の環境や心境の変化が一番大きいと思います。今、就活しているZ世代は、いわゆるスマホネイティブでパーソナライズされた情報に常に触れています。つまり彼らは「皆さんへ」というメッセージではなく、「あなたへ」というメッセージにしか興味を示しません。また自身のサーチ能力も高く、情報を調べて「これは正しい」「これは違う」という判断を瞬時に下します。学生の情報リテラシーの変化から、よりパーソナライズされた採用手法が生まれ、どんどん細分化されていったのだと考えられます。
――企業側にも変化はあるのでしょうか。
コロナ禍の影響により、事業モデルの転換を迫られている企業は非常に多いと感じています。企業が事業モデルの転換をしようとすると、組織の在り方自体を変化させる必要があるため、今まで採用しなかったタイプの人材を求める企業が増えてきます。
以前の採用は、優秀な人材を採用する「ハイパフォーマーモデル」でしたが、企業のニーズが変化してきて「多様/異能な人材」を求めるようになってきました。今まで自社で実績を上げてきたタイプの人材は今まで通りの採用活動を行っていれば出会えます。しかし、それと異なるタイプの人材には黙っていても出会えないため、企業側が異なるアプローチを強化している、ということでしょう。
重要なのは手法ではなく、採用目的と自社の価値に目を向けること

――このように多様化する採用手法の中で、注目している手法を教えてください。
採用活動を成功させるためには、「出会う」→「つかむ」→「口説く」という一連の流れを整備する必要があります。その流れをしっかりと理解した上で、総合的な採用戦略を組み立て、求める人材に適した手法を選択する必要があります。採用担当者に知っていただきたいのは、採用手法はあくまでも手段でしかなく、目的をはっきりさせることが重要ということです。
採用手法が多様化したことで、今まで会えなかった人材、地方の学生や上位校の学生とも出会えるチャネルは増えました。企業にとっては母集団を形成しやすくなっていると言えるでしょう。しかし、その分、学生は複数内定をもらうことが当たり前になっていますから、内定辞退や承諾後の離脱なども増えています。こういった状況だからこそ、企業は母集団を形成し、自社に興味を持ってもらい、入社してもらう、という採用プロセス全体の見直しが必要とされています。
――手法ではなく、目的とプロセスの構築が大事ということですね。
そうです。「出会う」という観点から言えば、ダイレクトリクルーティングや新卒紹介、リファラル採用は今後も伸びていくと思います。しかし、相対的に見れば、「つかむ」「口説く」のほうが重要になってくるので、リクルーターや面接官のレベルアップに取組む必要があると考える企業も最近では増えてきましたね。

――採用戦略を描き、採用に至るまでのストーリーを描くことが重要ということでしょうか。
そうですね。企業の採用力の強化は経営そのものなので、コンセプトとストーリーが重要となります。企業は、何かしらの価値に立脚したコンセプトを構築し、一貫性のあるメッセージを発信する必要があります。コンセプトがしっかりしていないと、学生が受け取る膨大な情報量の中で記憶に残すことができません。
また、採用活動において、前半のコミュニケーションは複数人に対して行われますが、後半はどんどん個別化していきます。すなわち、リクルーターや面接官がコンセプトを自らの言葉でしっかり語れなくてはならないということです。
最近の学生はサーチ能力が高いので、コンテンツをどこかに上げれば必ずアクセスしてくれます。企業は、自社の価値やコンセプトを見直し、採用したい人物像を設定した上で、集める方法を考える、という一連の流れを行っていただきたいと思います。
後編:採用課題別に解説!取り入れるべき採用手法とポイントとは【採用賢者に聞く 第16回】
また、Thinkings株式会社では採用業務を大幅に効率化する「採用管理システムsonar ATS」を提供しています。「事務作業に追われ、候補者と向き合う時間がない...」とお困りの方は、ぜひ一度資料をご覧ください。
▼導入企業様からはこんなお声をいただいています▼
「採用担当の残業時間が前年より83%減少した」
「まるで採用担当がもう1人増えたみたい」
「最終面接への移行率が60%→90%に増加した」
⇒採用管理システムsonar ATSの資料はこちらから

ジャンプ株式会社
代表取締役
リクルート代理店勤務の12年間で、のべ400社以上の採用活動を支援。1000人を超える代理店営業の中で、MVPを5度受賞。多数のベストプラクティスを生み出す。2008年、ジャンプ株式会社を設立。「働きたくなる会社を日本中に」をミッションに、採用力強化に特化した事業を展開。20年以上の採用コンサル経験をもとに「採用戦略のフレームワーク」を日本で初めて体系化。採用戦略オープン講座「STRUCT ACADEMY」を立ち上げ、主宰として指導にあたる。リクルート代理店勤務の12年間で、のべ400社以上の採用活動を支援。1000人を超える代理店営業の中で、MVPを5度受賞。多数のベストプラクティスを生み出す。2008年、ジャンプ株式会社を設立。「働きたくなる会社を日本中に」をミッションに、採用力強化に特化した事業を展開。20年以上の採用コンサル経験をもとに「採用戦略のフレームワーク」を日本で初めて体系化。採用戦略オープン講座「STRUCT ACADEMY」を立ち上げ、主宰として指導にあたる。https://jumpers.jp/