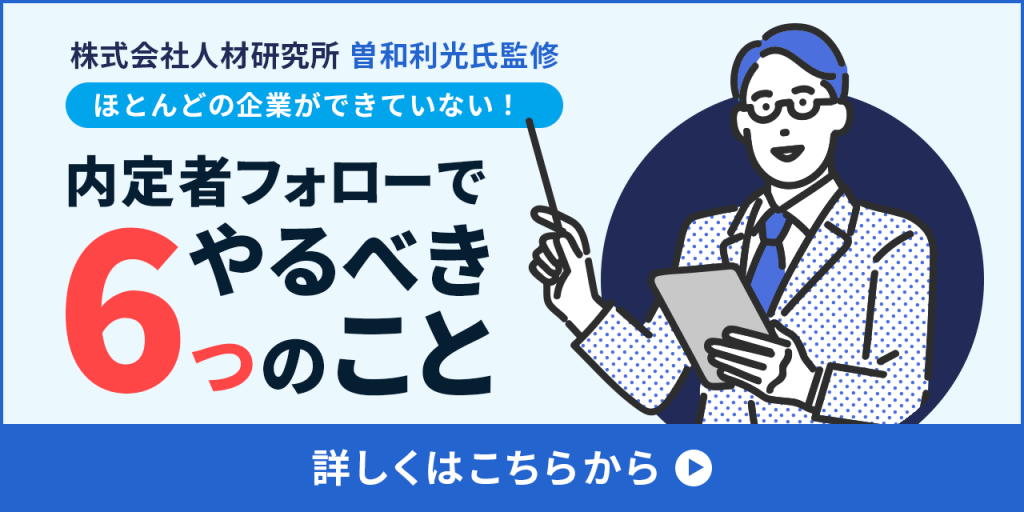お役立ち記事
採用管理システム(ATS)が必要な企業とは?開発企業に聞く「検討ポイントと導入のタイミング」
-
- HRテックかんたん解説
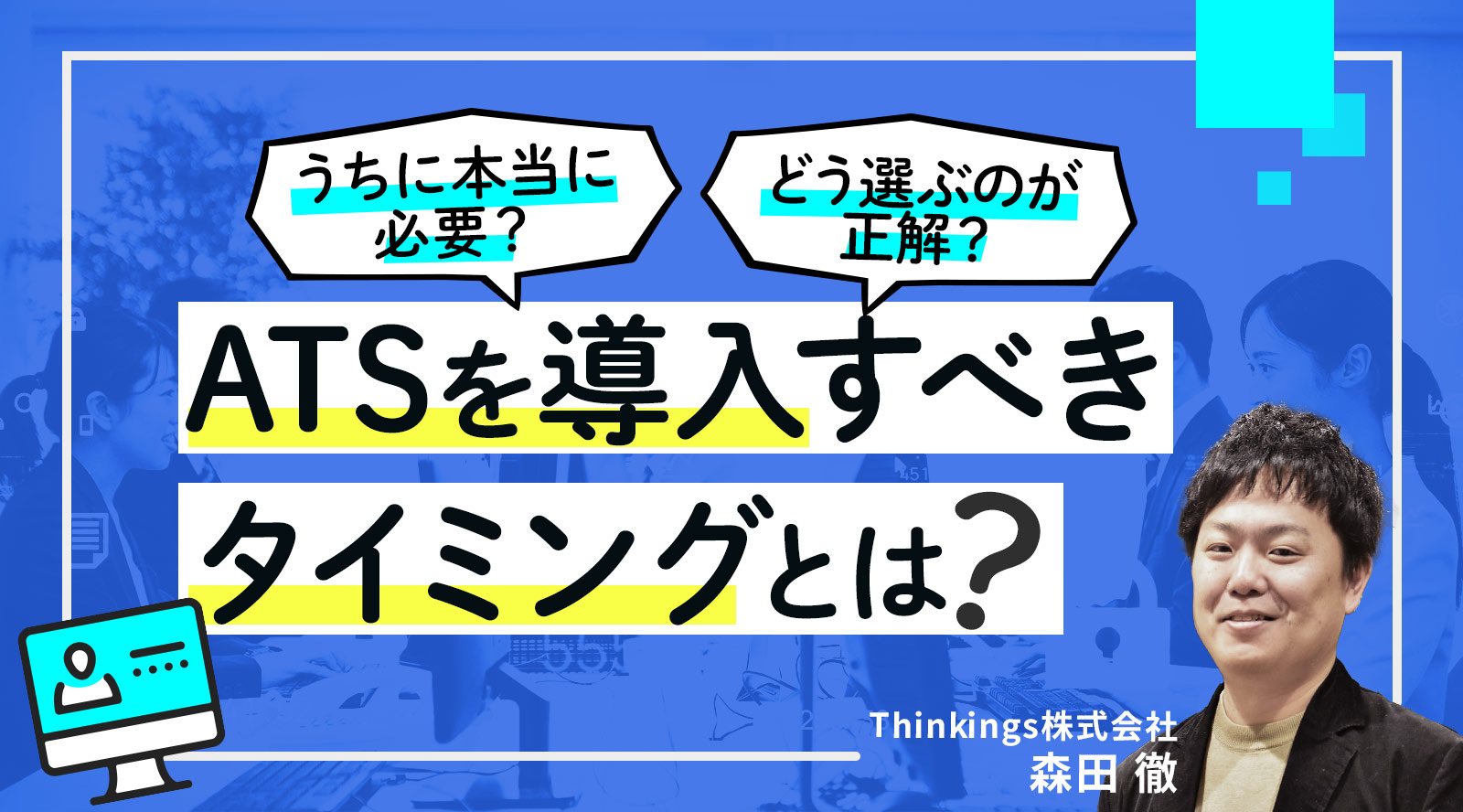
採用業務には、応募情報の管理、面談日程の調整や選考フローの設計など、多くのタスクがあります。このような多岐にわたるタスクを効率よく実施するために開発されたのが採用管理システム(ATS)です。しかし、ATSを導入するにしても、何を基準に選べばよいのか、そもそも本当に導入すべきなのか判断がつかないという採用担当者も多いのではないでしょうか。今回は、採用管理システムsonar ATS開発企業であるThinkings株式会社の取締役・森田 徹氏に、ATSの選び方や導入に向いている企業の特徴などについて、詳しく話を聞きました。
採用業務の膨大な作業を効率化する採用管理システム

―採用管理システム(ATS)とはどのようなツールか改めて教えてください
ATSには、二つの役割があります。
一つは、応募者とその選考状況を一元管理することです。マーケティングで使われるMAやSFAに置き換えて説明すると分かりやすいかもしれません。マーケティングツールが、さまざまなチャネルからお客様のリードを獲得して管理するように、ATSも各種求人メディア、エージェント、リファラルなど多彩なチャネルから応募者を取りまとめて管理していきます。ATSを見れば、自社の採用状況の全体像を把握できるだけでなく、応募者個々人の状態もわかるため、必要に応じてコンタクトを取ることができます。
もう一つが、社内外コミュニケーションの円滑化です。採用活動は、採用担当者だけでは完結しません。役員や現場の社員に面接官を務めてもらうことや、エージェントに協力を仰ぐこともあります。そのときにATSを活用することで、応募者の情報や選考の結果などをスムーズに情報共有することができます。
―ATSを導入する効果やメリットについて教えてください。
採用活動において採用担当者が表に出るのは応募者と接点を持つ場面だけに思われがちですが、その裏にはみなさまご存知のとおり、膨大な社内調整や事務作業が隠れています。そのような裏の作業を、ATSは効率化し、業務の質を高いレベルでキープすることを目指せます。
採用活動は、一人ひとりの応募者に対して抜け漏れがない状態で、すべてのワークフローを回す必要があります。それでいて、採用したいポジションとの適性を加味し、それぞれの応募者に対して適切なアプローチを求められるため、個別性の高い業務ともいえます。それらの業務をサポートできることが、ATSの大きなメリットだと思います。
導入の判断基準は、採用活動に“負”を感じるか否か
―ATS導入を迷っている企業様も多いと聞きます。実際、どのような声を聞きますか?
よく伺うのは、「採用人数が少ないからATSは不要」「ナビ付帯のシステムとエクセルで十分」といった声です。そもそもATSを使わなくても採用活動は可能なので、未導入のお客様は、何を期待して導入すればよいかイメージができないこともよくわかります。ただ、現在の採用活動に、以下の2つのような負 を感じているなら一考の余地があると思います。
採用の量・質に満足していない
採用目標と現状にギャップがある場合、それを埋めるための手段としてATSが役立つ可能性があります。ここで注意したいのが、「ATSの導入」=「採用の量・質の解決」に直結する魔法の杖ではないということです。たとえば、採用の量を増やすために、母集団を大きくしたいとしましょう。そのために、より多くの媒体を使うことになったとします。当然、管理する媒体や、やりとりする応募者の数は増えていくでしょう。そのときに、それまでと同様の質で採用活動ができるか、という課題が出てきます。ここで、ATSを導入するかどうかを判断することになります。
採用課題の解決に向け、何か新しい施策に取り組もうとするなら、採用活動のインフラとしてATSを導入する意味があると思います。新しいチャレンジに穴の空いたバケツで臨むより、ヌケモレのないしっかりとしたバケツを用意したほうが、成功の確度が上がるはずです。
しかし、ATSがなくても従来のワークフローや管理方法で業務の質を担保した採用活動できる、というのであれば、導入する意味はないでしょう。ATSを導入しても、採用業務のタスクが減るわけではありません。 ヌケモレのない高品質で、より多くのタスクをこなせるようにするのが役割だということを改めて知っていただけると迷いが減るのではないでしょうか。
採用活動で、やるべきことができていない
これは、課題が顕在化しています。つまり、タスクが膨大すぎて採用担当者の手が回っていない状態のこと。それによってフォローすべき応募者をフォローできなかったり、対応が遅れて選考辞退されてしまったりすることが起きているかもしれません。これでは、採用活動全体の状況も把握できないでしょう。そして、状況がわからないと、当然PDCAサイクルを回せません。このような場合、採用活動は停滞していると言えます。そんなときにはATSを導入し、まずは採用活動のタスクをきちんとこなすことができるようにしましょう。すると本来の解決すべき課題が見えてくるかもしれません。

―逆に、ATS導入にあまり成果が期待できないケースはあるのでしょうか?
これは正直、判断が難しいですね。何をもって成果とするのかは、お客様によって違いますから。一人の採用にどれくらいのコストをかけられるのか、どれくらいの工数なら妥当なのか、基準はお客様それぞれの課題感や経営判断によります。そこにATS導入の投資対効果を感じられないなら、導入は見送ったほうがよいでしょう。導入目的が薄いケースは成果につながらないとも言えるでしょう。
選定のポイントは、自社とのフィット度合い
―ATSは、さまざまなベンダーが提供しています。選定する際に押さえておきたいポイントはありますか?
先ほどお話しした投資対効果で、何を優先するかにもよりますが、判断の軸として見ておいたほうがよいものを、いくつかお伝えします。
UI/UX(操作性・使い勝手)などが、自分たちにマッチしている
端的に言うと、自分たちが使いやすいツールかどうか、ということです。“自分たち”には、採用担当者だけでなく、社内で協力してもらう現場の社員や社外のエージェントなど、採用にかかわるすべて人が含まれています。その人たちが、ストレスなく使えることがATS選定にあたっての重要なポイントです。特に現場の社員にとっては、採用がメインの業務ではありません。面接時に応募者の情報を確認する、面接の結果を入力する、といった作業をATSで実施してもらうためには、社員にとって、できるだけ負担や抵抗の少ないUI/UXのものを選んでください。
自社で利用しているシステムと連携しやすい
採用に限らず、複数のシステムを利用していると、あるシステムの出力したデータを、別のシステムへと手入力する、という二度手間が発生するケースが少なくありません。例えば求人サイトの登録情報をATSに移すとか、内定者のデータをATSから人事管理システムに移す、などのケースが考えられます。連携という観点で言うとデータ移動だけでなく、オンライン面接ツールや適性検査などの案内をATSから配信したり、それらの結果をATSに格納するといった連携も考えられます。せっかく効率化を目指して導入するATSなので、社内で利用しているほかのシステムやサービスと連携しやすいことも、選定する際のポイントになります。
ATSベンダーと、自社の成長戦略が合っている
採用活動は、企業が存続していく限り、ずっと続くものです。たとえば導入企業側の場合、今は駆け出しのベンチャーでも、ゆくゆくは上場を目指している企業なら、その成長のフェーズに応じて、採用活動のスタンスも変わってくるでしょう。一方ATSは、ベンダーによっては中途採用、アルバイト採用など特定の採用に特化したものも少なくありません。このほか、大企業向け、中小企業向けなど、企業規模に応じて最適化されたATSもあります。ATSベンダーがターゲットにしている企業と、自社の将来像が重ならない場合、たとえ一時的にそのATSとフィットしていても、いずれは合わなくなるでしょう。一度導入したATSをリプレイスするとなると、それなりに大きな投資が必要です。変動性が高い時代なので、今後の展望を明確に描くのは容易ではないと思いますが、自社の成長戦略とATSベンダーの方向性は、ある程度確かめておくほうが、リスクヘッジになると思います。
――ATSベンダーとの打ち合わせやヒアリングで、確認しておいたほうが良いポイントなどはありますか?
今、採用活動で困っていることをATSでどのように解決できるのか、“How”を聞いてください。そのやり方が、自社に合っているか、自社でできるのかということは、大きな目安になるはずです。
というのも、自社の業務フローを全く変えずに対応できるシステムは存在しないのです。システムを導入するということは、少なからず現在の業務フローや、やり方を変えなくてはなりません。むしろ、システムに合わせて業務を最適化するほうが、得られるものが大きいと思います。しかし、お客様によって変更の許容範囲は異なり、どうしても変えられないという部分も中にはあるでしょう。そのため、ATSによる課題解決の“How”を知ることは重要になってくるのです。
―ATSの導入を検討する時期やタイミングを教えてください。
新卒採用であれば、応募者数が500~1000人など、一定の単位を超えたタイミングが一つの目安です。また、前述したように、募集のチャネルが増えるときも、検討したほうが良いタイミングだと思います。
中途採用であれば、募集職種が増えるタイミングです。中途採用は、入社タイミングやポジションがバラバラのため、個別対応が必要になります。私の経験値ですが、募集しているポジションが5職種以上になると、日々の採用業務を回すのが困難な日も…。そのときが、ATS導入を検討するタイミングです。
―ATSを導入するにあたって、どれくらいの期間を見ておけばよいでしょうか?
これはベンダーによって異なりますし、お客様のニーズに応じて変わる、というのが正直なところです。極端な話、「明日から使いたい!」ということなら、ベストプラクティスの設定をそのまま使って、スピード導入するのも不可能ではありません。
しかし、現実的には、採用活動は100社100様なので、採用活動の現場で起こっていることを丁寧にヒアリングし、フィットさせていく必要があります。また、ツールの特徴や強みを生かして導入しようと思ったら、社内のフローやルールの見直しも必要です。そうなると、お客様によっては関係各所との調整や、事前のテストなども検討・実施しなければなりません。そのようなもろもろの工程があるため、当社の場合は、導入には平均1カ月はかかるものとお客様にお伝えしています。

ATSは、メールや表計算ソフトと同じ「当たり前に使うべきツール」
―最後に、採用活動において、ATSとはどのようなツールでしょうか。
ひと言で表せば、「当たり前に使ったほうが良いツール」です。今、仕事で使われているメールや表計算ソフトなどと同じレベルで、ATSがあったほうが採用業務ははかどるでしょう。そして、そのベースの上に立つことで、よりレイヤーの高い、本質的な採用課題に取り組めるようになるはずです。それこそが、私たちThinkingsの目指す世界です。今後も、誰もが当たり前に使うツールとして、ATSの価値を広めていきたいと考えています。
また、Thinkings株式会社では採用業務を大幅に効率化する「採用管理システムsonar ATS」を提供しています。「事務作業に追われ、候補者と向き合う時間がない...」とお困りの方は、ぜひ一度資料をご覧ください。
▼導入企業様からはこんなお声をいただいています▼
「採用担当の残業時間が前年より83%減少した」
「まるで採用担当がもう1人増えたみたい」
「最終面接への移行率が60%→90%に増加した」
⇒採用管理システムsonar ATSの資料はこちらから

Thinkings株式会社
取締役
2006年に北海道大学経済学部を卒業。在学中はアカウンティングを専攻。2006年に人材コンサルティング会社へ入社し、大手企業からベンチャー企業まで数多くの新卒・中途採用の成功スキーム構築を支援。 2013年、イグナイトアイ株式会社の創業メンバーとして参画し、sonar ATSのマーケティング・セールス部門を管掌。現在はThinkings株式会社にてプロダクトマネジメントを担当。